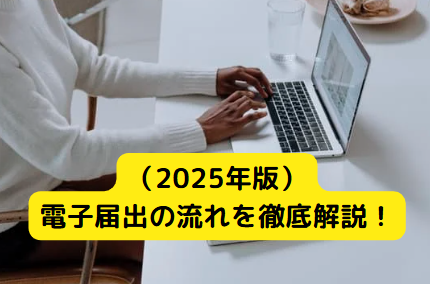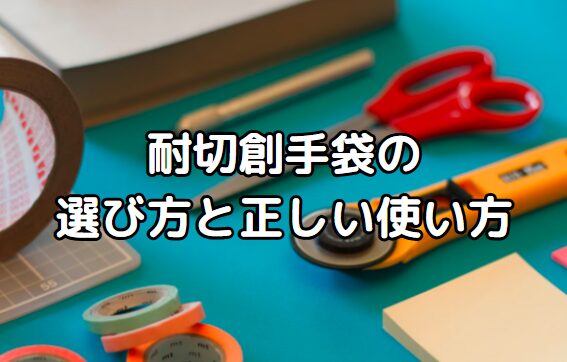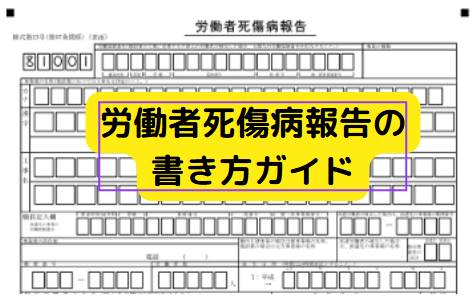
労働災害が発生した際に必ず必要となるのが「労働者死傷病報告」です。これは労働安全衛生法に基づいて事業者に課されている義務であり、一定の災害については遅滞なく所轄の労働基準監督署へ提出しなければなりません。
本記事では、労働者死傷病報告の概要、提出義務の範囲、報告様式(様式第23号)、提出期限、電子申請方法など、安全管理者が押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。
労働者死傷病報告とは?安全衛生法で定められた報告義務

「労働者死傷病報告」は、労働災害が発生した際に、事業者が労働基準監督署へ報告するための書類です。これは、労働安全衛生法第100条に基づいて義務付けられており、労働災害の規模や内容に応じて、所定の様式で報告しなければなりません。
この報告は、単なる行政手続きではなく、労働災害の再発防止に向けた国の統計・指導の基礎資料としても活用される重要なものです。そのため、報告内容はできるだけ正確かつ詳細に記載することが求められます。
報告が必要なケースとは?提出義務の対象となる災害の範囲

報告義務があるのは、すべての労働災害ではなく、以下のように区分されています。
「死亡災害」の場合
労働者が業務中の事故や疾病により死亡した場合は、遅滞なく(災害発生後速やかに)報告する必要があります。
「休業4日以上の負傷・疾病」の場合
労働災害により、労働者が4日以上休業した場合も、報告の対象です。これは通勤災害ではなく「業務災害」が該当します。
ケガが発生してから遅滞なく(2週間以内が通説です)、届出するようにしましょう。
「休業1~3日の負傷・疾病」の場合
これらのケースでは、四半期ごとの定期報告が必要となる場合があります。すべての労働災害が報告対象になるわけではありませんが、小さなケガでも注意が必要です。
休業がない負傷・疾病の場合
休業がない場合、死傷病報告書の作成は不要です。
※死傷病報告書の「休業日数」はケガをした翌日からカウントします。
(例)勤務時間中にケガをしたため、通院するため業務を中断した。病院から直帰したが、翌日はいつも通りの時刻から業務を開始した。
⇒この場合、休業日数は「ゼロ」となりますので、死傷病報告の作成は不要です。(労基署への報告も不要です)
報告書の様式と記載項目|様式第23号の使い方
報告書は「様式第23号」(労働者死傷病報告)を使用します。令和3年に様式が一部改正され、現在は電子申請にも対応した形式となっています。
主な記載項目は以下のとおりです:
- 事業場の名称・所在地・業種など基本情報
- 被災者の氏名・性別・年齢・職種
- 災害発生日時・場所・作業内容
- 災害の状況(どのような状況で起こったか)
- 受傷部位、負傷の程度
- 原因分析・再発防止策(任意記載)
✅記入時のポイント
- 災害の経過や原因は具体的かつ簡潔に(例:「転倒」「切創」「巻き込まれ」など)
- 負傷名や休業日数は医師の診断書などを基に記載
- 報告は災害発生後速やかに(目安:発生日から5日以内には提出)
書き方に迷った場合は、厚生労働省や労働基準監督署が公表している記入例を参考にするとスムーズです。
(参考例)※工場作業中の転倒災害を想定しての記入例です。
様式第23号(第100条関係)
【事業者情報】
1.報告者の氏名(法人名):株式会社○○製作所
2.事業場の名称:○○製作所 第2工場
3.事業場の所在地:東京都大田区○○町1-2-3
4.業種:機械器具製造業
5.労働保険番号:13-12345678-000
【災害発生の情報】
6.災害発生年月日:令和6年3月15日
7.災害の種類:負傷(転倒)
8.被災者数:1名
9.災害発生場所:工場内組立ライン横通路
10.災害発生時の作業内容:部品運搬作業
【被災者情報】
11.氏名:山田 太郎
12.性別:男
13.年齢:45歳
14.職種:製造職(組立作業員)
15.入社年月日:平成30年4月1日
【災害の状況】
16.災害発生の経過及び原因:
部品を運搬中、通路にあった空パレットに足を引っかけ転倒し、右足首をひねる。
現場の整理整頓不足が原因と考えられる。
17.受傷部位・傷病名:右足首捻挫(靭帯損傷)
18.休業日数(見込み):10日
19.死亡の有無:無
【報告日・提出者】
20.報告年月日:令和6年3月18日
21.報告者署名(記名押印):株式会社○○製作所 代表取締役 佐藤一郎
提出期限と提出先|遅延した場合のリスクもチェック
報告の提出には期限が設けられています。
- 死亡・休業4日以上の災害:災害発生後遅滞なく提出
- 休業3日以下・無災害:四半期ごとの報告
提出先は、事業場を管轄する労働基準監督署です。間違って他の管轄へ送らないよう、所在地を確認しておきましょう。
なお、提出義務を怠ったり、虚偽の報告を行った場合には、50万円以下の罰金が科されることがあります(労働安全衛生法第120条)。
報告は、法令遵守と安全管理体制の信頼性維持の観点からも、確実に行う必要があります。
電子申請も可能!労働者死傷病報告の提出方法まとめ

近年では、電子申請(e-Gov)を活用して報告書を提出する事業者も増えています。その際には、GビズID(gBizID)を取得し、電子署名を使って申請します。
● 電子申請の流れ(概要):
- GビズIDにログイン
- 労働者死傷病報告の様式を選択
- 必要事項を入力し、電子署名を付与
- 提出完了通知を受領
● 紙での提出が必要なケース:
- GビズIDの取得が間に合っていない
- 電子申請に不慣れな小規模事業場
※紙で提出する場合は、所轄の労働基準監督署に持参または郵送します。
それぞれの方法にメリットがありますが、電子申請は控えの保存や確認もスムーズなため、今後の主流となると考えられています。
まとめ|安全管理体制の中での報告体制の整備が鍵
労働者死傷病報告は、労働災害が発生した際の法令上の必須対応です。報告を怠ると、法的リスクだけでなく、行政からの指導や監査の対象となることもあります。
また、報告書は単なる“義務”ではなく、災害の原因分析や再発防止につなげる重要な資料でもあります。普段から労働災害が発生した際の社内連絡体制や、報告フロー、様式の保管場所などを整えておくことが、安全管理の第一歩です。