
近年、職場におけるストレスやハラスメントが原因で、うつ病や適応障害などの精神障害を発症するケースが増加しています。
これらの精神障害が労災として認定されるためには、厚生労働省が定める「心理的負荷による精神障害の認定基準」を満たす必要があります。
本記事では、最新の改正ポイントを含め、精神障害の労災認定基準と申請手続きについて詳しく解説します。
精神障害の労災認定とは?

精神障害の労災認定とは、労働者が業務に関連して精神障害を発症した場合に、労働者災害補償保険(労災保険)から給付を受けることができる制度です。厚生労働省は、令和5年9月1日に「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、最新の社会情勢や医学的知見を踏まえた基準を設けています。
認定基準の対象となる精神障害
労災として認定される対象となる精神障害は、次のような診断名に該当するものです。
- うつ病(大うつ病性障害、気分変調症など)
- 適応障害
- 不安障害(パニック障害など)
- PTSD(心的外傷後ストレス障害)
- 双極性障害(躁うつ病)
※統合失調症や発達障害は、原則として対象外とされていますが、業務による著しい悪化が認められる場合は個別に判断されます。
労災認定の3つの要件
労災として認められるためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
✅対象となる精神障害であること
✅発病前の6ヶ月間に、業務による強い心理的負荷があったこと
✅業務以外の要因による発症でないこと
この3つの観点から、業務との因果関係が認められるかどうかが判断されます。
業務による心理的負荷の評価方法

労働基準監督署が精神障害の認定にあたって評価するのが、「心理的負荷評価表」です。これは、業務上の出来事について心理的な負荷の程度を「弱・中・強」に分類するものです。
例)
- 業務に関連し、他人に重度の病気やケガを負わせ、事後対応にも当たった(強)
- 客観的に相当な努力があっても達成困難なノルマが達成できず、事後対応にも多大な労力を費やした(強)
- 発病直前の連続した2か月間に、1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った(強)
- 1か月以上にわたって連続勤務を行った(強)
- 胸や腰等への身体接触を含むセクシュアルハラスメントであって、継続して行われた(強)
- 上司等から、人格否定や無視など精神的攻撃等を反復・継続するなどして執拗に受けた(強)
「強」と評価される出来事が発症前6ヶ月以内にあり、かつ明らかに業務によるものであれば、労災として認定されやすくなります。
業務と発症の因果関係の判断
精神障害が労災と認定されるには、「業務によって発病した」と合理的に判断できる因果関係が必要です。
以下の要素が考慮されます:
- 出来事の発生日と発症日との時期的近接性
- 出来事の具体性や重大性
- 被災者の行動や周囲の証言
- 医師の診断と所見
発症のきっかけが業務に明確に結びついていれば、私生活上のストレス要因があっても、労災と認定されるケースもあります。
ハラスメント・いじめ等による労災認定

ハラスメント(パワハラ・セクハラ・マタハラなど)は、精神障害の労災認定で特に注目される要因のひとつです。
厚労省の基準では、以下のような行為が「強い心理的負荷」として評価される可能性があります。
- 人格否定的な発言の継続
- 同僚の面前での叱責
- 社内での孤立化
- 身体的暴力を含む行為
これらの行為が事実として確認されれば、労災認定される可能性が高まります。
労災申請の手続きと必要書類
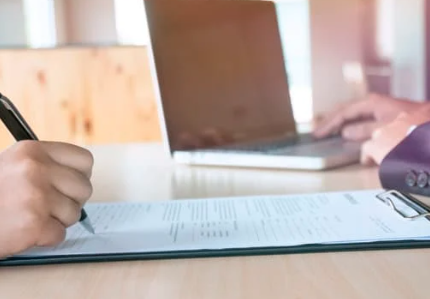
精神障害の労災認定を受けるには、以下の手続きを経る必要があります。
- 診断書の取得
- 労働基準監督署への申請(様式5号)
- 業務内容や出来事の証拠資料の提出
- 会社への照会(監督署が実施)
- 医師の専門意見(精神科医)
- 認定の可否判断
申請から結果通知までは半年~1年程度かかることが多く、書類の準備や証拠の確保が重要です。
企業が取るべき予防策と対応

企業側としては、精神障害による労災申請を防ぐためにも、次のような対策が求められます。
- ストレスチェックの定期実施
- ハラスメント対策の社内研修
- メンタルヘルス相談窓口の設置
- 勤務時間の管理(長時間労働の抑制)
- 人間関係のトラブル予防策の整備
また、労災申請が行われた場合には、被災者のプライバシーに配慮し、誠実かつ迅速に対応する姿勢が必要です。
まとめ

精神障害の労災認定は、見えにくい症状と業務との因果関係を判断するため、非常に慎重な審査が行われます。ハラスメントや過重労働が社会問題化するなか、企業・労働者ともにその基準を正しく理解し、早めに予防・対応策を講じることが求められています。
職場のメンタルヘルス対策を強化することは、従業員の安全と生産性の向上につながります。万一、精神障害を発症してしまった場合には、躊躇せず専門家や労働基準監督署に相談しましょう。



