
労災保険は、仕事中や通勤中に起きた事故や病気に対する重要な補償制度です。業務災害、通勤災害、複数業務要因災害など、さまざまなケースに対応しています。
万が一の事故に備えるため、労災保険の仕組みや対象となる災害について詳しく理解しておくことが大切です。
本記事では、労災保険の基本から給付内容、手続き方法までをわかりやすく解説します。
労災保険とは?基本的な仕組みと対象者
労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者が業務中や通勤中に被った災害(ケガや病気、障害、死亡など)に対して、必要な給付を行う公的保険制度です。事業主が加入し、労働者1人でも雇用していれば原則として適用されます。保険料は全額事業主が負担し、労働者の自己負担はありません。
労災保険が対象とする災害には、以下のようなものがあります
- 業務災害(仕事中に発生した災害)
- 通勤災害(通勤途中に発生した災害)
- 複数業務要因災害(副業・兼業など複数の仕事の影響で発生した災害)
給付内容には、医療費の補償だけでなく、休業中の所得補償や障害・死亡に対する補償など多岐にわたります。
業務災害とは|どのような事故や病気が該当するのか

業務災害とは、「業務遂行性」と「業務起因性」が認められる災害のことを指します。つまり、労働者が事業主の支配・管理下で業務に従事しており、その業務が原因となって災害が発生したと認められる必要があります。
【業務遂行性】とは
労働契約に基づき、使用者の指揮命令下にある状態であること(例:勤務時間内、職場内など)。
【業務起因性】とは
業務に内在または随伴する危険が災害の原因であること(例:作業ミスによるケガ、業務中の転倒など)。
業務災害の具体例
- 建設現場での高所作業中の墜落事故
- 倉庫での荷物運搬中のぎっくり腰
- 機械の操作ミスによる指の切断
- 工場内での感電事故
- 長時間労働による脳出血
ただし、以下のような場合は業務災害と認められない可能性があります
- 労働者の私的な行為中に発生した災害
- 故意または重大な過失による災害
- 業務とは無関係の自然発病(例:風邪など)
業務上の疾病の具体例と認定基準

労働者が業務に関連して発病した病気は、「業務上疾病」として労災保険の対象になります。厚生労働省が定める「労災認定基準」に従って、個別の状況を総合的に判断して認定されます。
主な業務上疾病の例
- 有害因子の存在(例:化学物質、粉じん、騒音、重作業など)
- 健康障害を起こす程度のばく露(作業時間や強度)
- 医学的に妥当な発症経過や症状
主な業務上疾病の例
- 騒音による感音性難聴(※2023年4月にガイドライン改正)
- 振動障害(チェーンソー作業など)
- 有機溶剤中毒(塗装業など)
- アスベストによる肺がん・中皮腫
- 重作業による腰痛や肩こり
- 長時間労働・ハラスメントによる精神障害(うつ病など)
業務上疾病の認定は、医学的知見と労働実態を踏まえて慎重に判断されます。
(関連記事)腰痛でも労災になる?認定のポイントと手続きの流れを徹底解説 | 安全の王道
複数業務要因災害とは?副業・兼業時代に知っておくべき補償内容
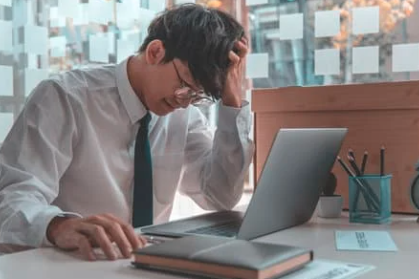
2020年の法改正により、「複数業務要因災害」の補償制度が導入されました。これは、複数の仕事に従事する労働者が、それぞれの業務の負荷の合算によって健康障害を発症した場合に、労災保険の給付を受けられる制度です。
複数業務要因災害のポイント
- 複数の雇用先での勤務が健康障害の原因であると認められる場合、すべての業務を総合的に評価
- 労災給付は「主たる業務」の保険者から支給
- 精神疾患や脳・心疾患が主な対象疾患
主な複数業務要因災害の具体例
- 日中は配送業、夜間は飲食業の勤務 → 合算労働時間が過労の水準を超え、心筋梗塞を発症
- 2つの職場でパワハラ・長時間労働 → うつ病を発症
副業・兼業が増える今後、重要性が増す制度といえます。
通勤災害の範囲と対象外となるケース

通勤災害とは、労働者が「住居と就業場所の間を合理的な経路および方法で移動する途中」に被った災害を指します。業務とは無関係でも、通勤中であれば保護の対象となります。
通勤に該当するケース
- 自宅と会社間の往復
- 主たる業務先と副業先の移動
- 出張先から自宅への帰宅など
通勤に該当しないケース
- 私的な用事(例:映画鑑賞、友人宅訪問)での寄り道・中断
- 通勤経路から大きく逸脱した場合
ただし、以下のような日常生活上必要な行為での逸脱・中断は例外的に認められます:
- 保育園や学校への送迎
- 通院
- 食料品などの日常生活物資の購入
これらは「合理的な範囲の逸脱」とされ、通勤災害とみなされる可能性があります。
労災保険給付を受けるための手続き
労災保険の給付を受けるには、所定の申請書を管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。労働者が申請することもあれば、事業者を通じて行うこともあります。
主な給付内容と申請様式
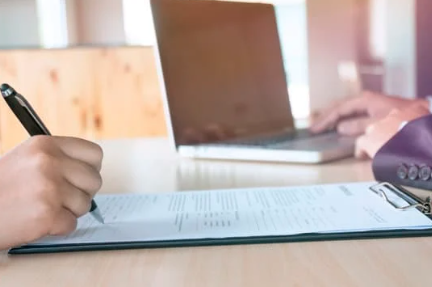
| 給付名 | 内容 | 申請様式 |
| 療養補償給付 | 治療費の全額補償(指定医療機関で無料) | 様式第5号など |
| 休業補償給付 | 休業4日目以降、給付基礎日額の80%相当 | 様式第8号 |
| 障害補償給付 | 後遺障害が残った場合に一時金または年金 | 様式第10号など |
| 遺族補償給付 | 労災死亡時に遺族へ支給(一時金・年金) | 様式第12号など |
| 通勤災害関連給付 | 通勤災害に対する療養・休業補償など | 上記と同様 |
近年は電子申請(e-Gov)も利用可能で、申請の手間が軽減されています。
(関連記事)【2025年最新】安全衛生法の届出を電子申請で!手続きの流れ・対応システム・メリットを徹底解説 | 安全の王道
まとめ|万が一に備えて知っておきたい労災の知識
労災保険は、仕事や通勤に伴うさまざまなリスクから労働者を守るための制度です。近年は多様な働き方に対応した補償範囲の拡充が進んでおり、特に副業・兼業者や精神疾患のリスクが高まる現代においては、その重要性が増しています。
労働者本人はもちろん、企業の安全管理担当者も制度を正しく理解し、労災発生時に迅速・適切に対応できる体制を整えることが求められます。制度を知っているかどうかで、受けられる補償や生活への影響が大きく変わることもあります。
日頃から最新の情報に触れ、万が一の際にも冷静に対応できるよう準備しておきましょう。


