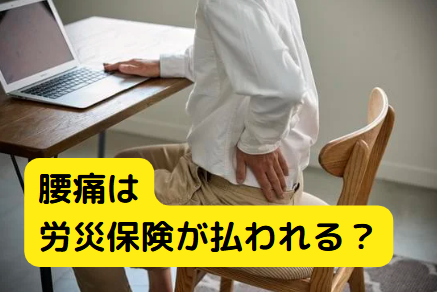
腰痛は多くの労働者が抱える職業病のひとつです。しかし、「この腰痛は労災にあたるのか?」と悩む人は少なくありません。実際、腰痛は労災認定されるケースもあれば、されないケースもあります。
本記事では、厚生労働省が示す「腰痛の労災認定基準」や、認定されるための要件、申請手続きの流れ、実際の認定事例などをわかりやすく解説します。
腰痛に悩む労働者や、安全衛生を担当する管理者の方にも役立つ情報をお届けします。
腰痛は労災になるのか?基本的な考え方
腰痛は、現代の職場で非常に多く見られる身体的なトラブルのひとつです。建設業や運送業、介護職のような身体的負担の大きい職場はもちろん、長時間座りっぱなしのデスクワークでも腰への負担は蓄積されます。
では、その腰痛が「労災」として認められるケースとは、どのような状況なのでしょうか?
労災認定の可否は、「業務との因果関係」が明確に認められるかどうかが鍵になります。
労働災害として認定されることで、療養補償や休業補償などの保険給付を受けることができます。
厚生労働省による「腰痛の労災認定基準」とは

厚生労働省は、腰痛についての労災認定基準を明確に定めています。主に、以下の2種類に分類されます。
「災害性の原因による腰痛」の認定基準
「災害性の原因による腰痛」とは、腰に受けた外傷によって生じる腰痛のほか、外傷はないが、次の具体例のように、突発的で急激な強い力が原因となって筋肉等(筋、筋膜、靱帯など)が損傷して生じた腰痛を含みます
- 重量物を持ち上げた瞬間に「ギクッ」と痛めた
- 転倒や滑落などの事故で腰を負傷した
- 突発的な動作中に腰に激痛が走った
労災補償となる要件は、次の要件をどちらも満たすものです。
✅腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
✅腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること
一般的に「ぎっくり腰」は、日常的な動作の中でも生じるため、仕事中に発生したとしても、ただちに労災補償の対象とはなりません。
業務を行っていたときの動作や姿勢の異常性などから、腰への強い衝撃があった場合には、労災補償の対象となります。
「災害性の原因によらない腰痛」の認定基準
「災害性の原因によらない腰痛」とは、日々の業務による腰部への負荷が徐々に作用して発症した腰痛をいい、その発症原因により、次の①と②に区分して判断されます
筋肉等の疲労を原因とした腰痛
次のような業務に3か月以上(短期間)従事したことによる筋肉の疲労を原因として発症した場合に、労災補償の対象になります。
- 約20㎏以上の重量物または重量の異なる物品を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う業務
- 毎日数時間程度、腰にとって極めて不自然な姿勢を保持して行う業務
- 長時間立ち上がることができず同一の姿勢を持続して行う業務
- 腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務
骨の変化を原因とした腰痛
次のような重量物を取り扱う業務に相当長期間(約10年以上)にわたり継続して従事したことによる骨の変化を原因として発症した腰痛は、労災補償の対象となります。
- 約30㎏以上の重量物を、労働時間の3分の1程度以上に及んで取り扱う業務
- 約20㎏以上の重量物を、労働時間の半分程度以上に及んで取り扱う業務
腰痛は加齢によって発症することも多いので、労災補償の対象と認められるためには、「通常の加齢による骨の変化の程度を明らかに超える場合」と認められる必要があります。
労災認定される主な業務内容と事例
腰痛の労災認定がなされやすい代表的な業務例をいくつか挙げてみましょう。
重量物の運搬作業

倉庫業や運送業では、重量物の持ち運びが日常的にあります。特に、繰り返し同じような動作をすることで腰への負担が蓄積されるケースが多く、労災認定につながる可能性があります。
長時間の同一姿勢作業

製造業での立ち作業や、オフィスでの長時間のデスクワークなど、同じ姿勢を長時間保つ作業もリスク要因です。慢性的な腰痛が認められ、業務との関連が明確であれば労災対象になり得ます。
介護・看護業務での腰への負担

高齢者の移乗介助や体位変換など、腰に負担のかかる動作を日常的に行う介護・看護職も、腰痛による労災認定の対象となりやすい職種です。介護現場では、移乗補助具などの使用状況も考慮されます。
労災申請の手続きと必要書類
腰痛が労災の可能性があると判断された場合、以下のような手続きが必要になります。
労働者死傷病報告の提出
まずは、事業者が「労働者死傷病報告」を所轄の労働基準監督署に提出します。休業が4日以上となる場合は、発症後遅滞なく提出する必要があります。
(関連記事)労働者死傷病報告とは?提出義務・様式・電子申請まで安全衛生法に基づいて解説 | 安全の王道
医師の診断書の添付
労災保険の給付を受けるためには、医師による腰痛の診断書が必須です。この際、業務との因果関係を補強する記載があると、認定されやすくなります。
労働基準監督署での審査の流れ
申請後は、労働基準監督署によって業務との因果関係や、作業内容の確認が行われます。場合によっては、現場調査や面談が実施されることもあります。
労災認定されやすくなるためのポイント
腰痛の労災申請を行う際、以下の点を押さえておくと認定されやすくなります。
作業記録や日報の記載
腰に負担がかかる作業があったことを、作業日報や業務日誌などで記録しておくことは非常に有効です。作業時間や内容が具体的に記録されていると、因果関係が認められやすくなります。
発症時の状況証拠の収集
腰痛が発症した際の状況(作業内容、姿勢、周囲の証言など)をできるだけ詳しく記録しておくことが重要です。写真や動画などがあるとさらに効果的です。
会社との連携の取り方
会社側が労災申請に協力的であることも、スムーズな手続きに不可欠です。安全衛生委員会などでの情報共有や、職場環境の改善にもつながります。
安全衛生管理者が気をつけるべき職場の腰痛対策
安全衛生管理者にとって、腰痛は重大な労働災害リスクのひとつです。予防のためには、以下のような対策が求められます。
- 腰部サポーターや移乗補助具などの用具の導入
- 作業姿勢の改善指導(腰を曲げない持ち上げ方など)
- 作業間に適度な休憩を挟む勤務シフトの設計
- 腰痛予防のための職場体操や研修の実施
また、2023年(令和5年)に厚労省が改訂した「職場における腰痛予防対策指針」に基づき、職場のリスクアセスメントを実施し、リスク要因の除去・低減を図ることも求められています。
まとめ:腰痛と労災認定の理解が職場の安全を守る
腰痛は、放置すれば長期の休業や退職に至ることもある深刻な労働災害です。労災認定されるかどうかは、業務との因果関係をいかに明確に示せるかにかかっています。
労働者自身の記録や証拠の確保はもちろん、会社側も適切な対応と腰痛予防への取り組みが求められます。
正しい知識と予防策を身につけ、腰痛による労災リスクを最小限にとどめることが、安全で健康な職場づくりにつながります。


