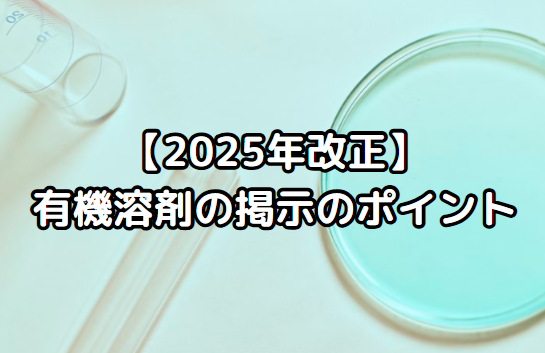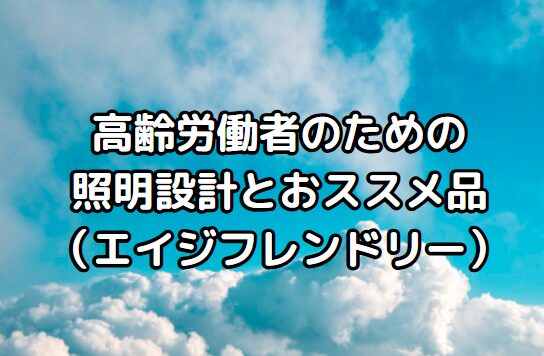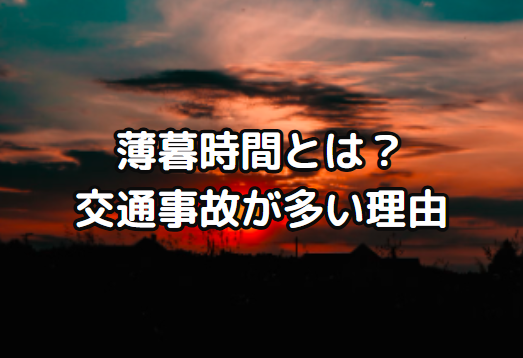
夕方の通勤時間帯や退勤後の移動中に発生しやすい「薄暮時間の交通事故」。日没直後の視界が悪くなる時間帯は、交通事故のリスクが急激に高まります。特に歩行者や自転車利用者が被害者になるケースも多く、企業として従業員の安全を守るためには対策が欠かせません。本記事では、薄暮時間に交通事故が多発する理由と、企業ができる具体的な予防策を、安全衛生の視点から詳しく解説します。
薄暮時間とは?交通事故が多発する理由
「薄暮(はくぼ)」とは、日没直後のまだ薄明るい時間帯を指します。気象庁では「日の入りから約30分程度」を目安としていますが、季節や天候によってその明るさは大きく変わります。
この時間帯は、ドライバーの視認性が急激に落ちる上に、歩行者や自転車側も自分の存在をアピールしにくくなるため、事故の発生率が上昇します。特に秋から冬にかけては、退勤時間と日没が重なるため、リスクがさらに高まります。

薄暮時間の交通事故に多いケースとリスク
警察庁の統計によると、薄暮時間帯の交通事故は以下のようなケースが多く見られます。
- 横断歩道での歩行者との接触事故
- 自転車と車両の接触事故
- 見通しの悪い交差点での出会い頭の事故
- 無灯火やライトの早期点灯不足による追突事故
薄暗い時間帯では、黒やグレーなど目立たない服装をした歩行者が見落とされやすく、ライトの点灯忘れや、早めの点灯を怠ることによって、発見の遅れが事故につながります。

高齢者が直面する薄暮時間の危険性
薄暮時間の交通事故で特に懸念されるのが高齢者の歩行中事故です。加齢により以下のようなリスクが重なります。
- 視力や暗順応能力の低下
- 聴覚の衰えによる接近車両の認知遅れ
- 歩行速度の低下による道路横断時間の延長
警察庁のデータでも、夕暮れ時に発生した歩行者事故の被害者の約6割が65歳以上の高齢者であると報告されています。横断歩道のない箇所で、横断してきた高齢者を車がはねてしまうケースが多くあります。企業としては、従業員本人だけでなく、通勤経路や地域の安全性、高齢者の家族がいる場合の配慮なども視野に入れて対策を検討すべきです。

黒い服装の見えにくさとその対策
視認性が低下する薄暮時間帯では、服の色が事故リスクに直結します。中でも黒・ネイビー・グレーといった暗色系の服装は、ドライバーからの視認が極端に困難になります。
実際の試験では、夜間の車のヘッドライト下で歩行者を認識できる距離は以下の通りでした。
| 服装の色 | 認識可能距離(ロービーム時) |
|---|---|
| 黒系 | 約25〜30メートル |
| 明るい色(白、黄色) | 約50〜70メートル |
| 反射材付きベスト | 約100メートル以上 |
車の停止距離は時速40kmでも30〜40メートル程度必要であるため、暗色系の服装では気づいたときには間に合わないのです。
対策:
- 明るめのアウターを着るよう奨励する
- カバンや靴に反射材を取り付ける
- 夜間用の反射タスキやアームバンドを会社で支給する
ハイビーム・ロービームの使い分けと注意点
ドライバーにとって、薄暮時間はライトの使い方が非常に重要になります。特にハイビーム(上向きライト)は視認距離が格段に伸びるため、歩行者や障害物の早期発見につながります。
ただし、対向車があるときのハイビームは相手の視界を奪うことにもなりかねません。以下の使い分けが必要です。
- 対向車や先行車がいない:ハイビームで走行
- 対向車・先行車あり:ロービームに切り替え
- 交差点・横断歩道:一時的にハイビームで確認してから切替
また、企業側が従業員ドライバーに対して、「ライトを積極的に使う」ことを指導することで、見落としによる事故を防ぐ効果が期待されます。

企業ができる交通事故予防策
企業ができる安全衛生対策には、次のような具体的なものがあります。
従業員への安全教育の実施
まず重要なのは、「薄暮時間帯は事故が多い」という認識を全社員に共有することです。通勤時や外出時のリスクについて、安全衛生教育の一環として定期的に周知しましょう。危険性を認識するだけでも、自然と運転は丁寧になり、事故の発生率は少なくなるものです。
チェックリストやポスター、社内メールなどを活用して、以下のような行動を促します。
- 車はライトを早めに点灯する(目安は16時前後)
- 自転車利用者は反射材やライトの装着を忘れずに
- 歩行者は明るい服や反射素材を着用する
高視認性の装備支給
夜間や薄暮時間帯に屋外作業や移動がある業種の場合、反射ベストや高視認性のジャンパーなどを支給しましょう。安全衛生法では義務とはされていませんが、労災防止のためには非常に効果的です。

通勤中のカバンや自転車に「反射ベルト」をおススメするよ。
かっちーが働いていた会社では、全員に反射ベルトを配っていたよ!
勤務シフトや退勤時間の工夫
秋冬は日没時間が早いため、繁忙期や特定業務に限ってはシフトの前倒し・後ろ倒しを検討するのも一つの手です。通勤時間をずらすだけで事故リスクは大きく下がる場合もあります。
テレワークの導入やフレックスタイム制の活用も、間接的に通勤時の事故リスクを軽減する手段になります。

社用車の安全対策と管理
業務中の運転が多い場合は、以下のような社用車管理も有効です。
- オートライト機能の有効化
- ドライブレコーダーの設置と活用
- 車両の点検(ライトやウィンカーの正常作動確認)

企業のリスク管理として加害者側にならないことも重要だね!
通勤災害としての取扱いと企業の責任
従業員が通勤中に交通事故に遭った場合は、「通勤災害」として労災保険の対象になります。
しかし、その背景に安全教育の不足や装備不備など、企業の配慮不足があった場合は、社会的な責任を問われる可能性もあります。
予防的な対策を取っていたかどうかが、後の対応に大きく影響するため、会社としての備えは非常に重要です。
衛生委員会での取組みと継続的な安全対策
毎月の衛生委員会で、季節ごとの交通安全テーマを取り上げましょう。例えば10月〜12月は「早めのライト点灯」と「反射材着用の徹底」、3月〜4月は「新生活に伴う通勤経路の変更リスク」など、時期に応じた話題を扱うことで効果的な啓発が可能になります。
委員会で出た意見をポスター化したり、全社メールで共有したりするのもおすすめです。

まとめ:企業が先回りして「事故ゼロ」を目指す
薄暮時間の交通事故は、「ちょっとした配慮」で大幅に減らせるリスクです。企業として、社員が安心して通勤・外出できるように、安全教育や装備の支給、勤務時間の工夫など、多方面から対策を講じていくことが重要です。
季節ごとの変化にも対応しながら、社員の命を守る安全衛生活動を積み重ねていきましょう。事故が起きてからでは遅いため、今すぐできることから始めるのが肝心です。