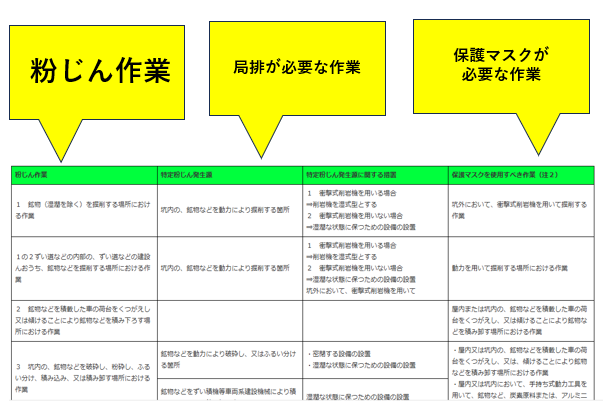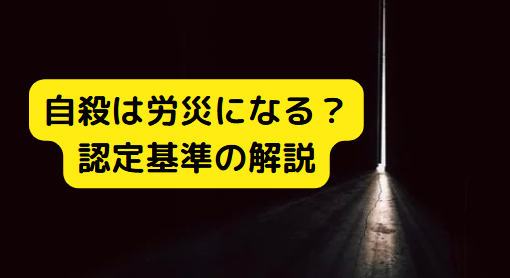
近年、職場のストレスやハラスメントなどによる精神的な負担が原因で、自殺に至るケースが社会問題となっています。
労働者が業務上の理由で精神疾患を発症し、自殺した場合、遺族が労災申請を行うことが可能です。
本記事では、「自殺した場合の労災認定」について、認定基準や具体的な手続きの流れ、必要な証拠などをわかりやすく解説します。労災認定を考えているご遺族や、企業の安全管理者の方にとっても重要な知識となるでしょう。
自殺は労災に認定されるのか?
労災保険制度では、業務上の原因で労働者が死亡した場合、遺族に対して補償が行われます。自殺についても例外ではなく、「業務による強い心理的負荷により精神障害を発病し、その結果として自殺に至った」と認められた場合には労災と認定される可能性があります。
ただし、単に業務が忙しかった、ストレスがあったというだけでは認定は難しく、一定の基準に照らして慎重に審査されます。
精神障害と労災認定の関係

厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」(令和2年改正、令和5年ガイドラインも反映)を定めており、自殺の場合もこの認定基準に基づき判断されます。精神障害が労災として認められるには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
(関連記事)【2025年版】精神障害の労災認定基準とは?ポイントをわかりやすく解説 | 安全の王道
自殺の労災認定における3つの要件
(1)精神障害を発病していたこと
医師による診断が必要です。うつ病やPTSD、適応障害などの精神疾患と診断されていた場合、該当する可能性があります。
(2)発病前おおむね6か月以内に、業務による強い心理的負荷があったこと
「ひどい長時間労働」「上司からのパワハラ」「顧客からの暴言」「重大事故への関与」など、精神的な負荷が客観的に明らかな場合が該当します。
(3)業務以外の要因による発病ではないこと
家庭内の問題や持病、金銭問題など、業務外の事情によって発病したと考えられる場合は、労災認定が困難になります。
認定されやすい業務上の出来事とは
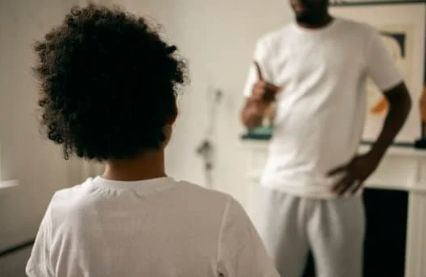
厚労省のガイドラインでは、具体的な心理的負荷事例が挙げられており、それぞれの事例について「強」「中」「弱」といった評価がされています。以下は認定されやすいとされる例です。
- 月100時間を超える長時間残業
- 突発的な異動や配置転換
- 上司・同僚からの執拗な嫌がらせやいじめ
- セクハラ・パワハラの被害
- 顧客からの理不尽なクレームの繰り返し
- 業務での重大ミスによる責任追及
これらが「強度の高い心理的負荷」と評価されると、認定の可能性が高まります。
労災申請の手続きと必要書類

遺族が行う申請
- 管轄の労働基準監督署へ申請
- 労働者死傷病報告や死亡診断書などの提出
- 関係者の証言、業務内容、勤務時間の調査
- 精神科医による専門的な判断を経て認定
提出が求められる主な書類
- 労災給付請求書(様式第5号)
- 死亡診断書または死体検案書
- 業務上の出来事の記録(勤務表、メール、日報など)
- 診療記録、カルテ
- 家族や同僚の陳述書
証拠が詳細で具体的であるほど、認定の可能性は高くなります。
遺族補償給付の内容
自殺が労災として認定されると、遺族には以下の給付が支給されます。
- 遺族補償年金または一時金:扶養状況によって支給額が変動
- 葬祭料:通常31万5000円または給付基礎日額の60日分
- 特別遺族給付金:一定の条件下で支給
労災保険による給付は原則として無税であり、民事訴訟などの慰謝料請求とは別に支給されます。
労災認定のハードルと対策

ハードルの一例
- 精神障害の診断がなかった場合
- 自殺の原因が業務以外にあると判断された場合
- 適切な証拠が不足している場合
対策
- 可能であれば、発病当時の診療記録やカウンセリング履歴を集める
- 職場での記録(上司とのやりとり、残業記録、ハラスメントの証拠)を整理する
- 労災に強い弁護士や社労士と連携する
また、企業側としても、ハラスメントや過重労働を未然に防ぐための体制整備が重要です。安全衛生委員会の活用や産業医面談の実施も有効です。
まとめ
自殺が労災と認定されるには、精神障害の発症、業務による強い心理的負荷、業務以外の要因の否定という3つの要件を満たす必要があります。認定のためには、具体的かつ客観的な証拠の提出が求められるため、申請には慎重な準備が必要です。
企業としては、こうした悲劇を未然に防ぐためのメンタルヘルス対策の強化が不可欠です。労災認定は、ご遺族にとって重要な補償の手段であり、正当な権利です。必要に応じて専門家の助けを借り、手続きを進めていきましょう。