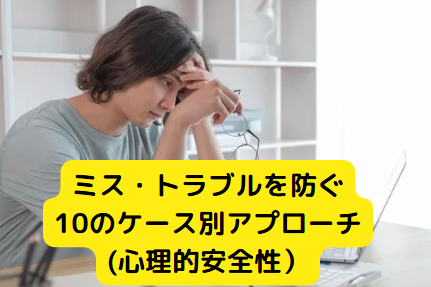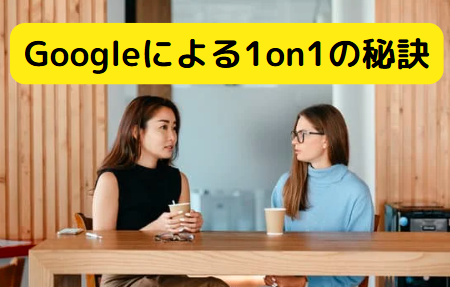
社員のエンゲージメントや生産性を高める手法として注目されている「1on1ミーティング」。中でもGoogleが実践している1on1の内容は、世界中の企業から注目を集めています。
本記事では、Googleが1on1をどのように位置づけ、どのような目的や内容で実施しているのかを詳しく解説します。また、実践のポイントや注意点、他社での応用方法も紹介します。効果的な1on1を導入したい経営者・マネージャー必見の内容です。
1on1とは? Googleが注目する理由
1on1(ワン・オン・ワン)とは、上司と部下が1対1で定期的に対話を行うミーティングのことです。週1回、30分程度が一般的な頻度とされており、業務の進捗報告だけでなく、キャリアの悩みや個人の課題なども話題に含まれます。
Googleが1on1に注目した背景には、次のような考え方があります。
- チームのパフォーマンスは「心理的安全性」と「信頼関係」に大きく左右される
- 従業員が率直に悩みを打ち明けられる場が必要
- 日常のマネジメントでは拾いきれない声を継続的に吸い上げる仕組みが必要
これらを実現するための仕組みとして、1on1は非常に有効と判断されたのです。
Googleにおける1on1の目的と位置づけ

Googleでは、1on1を単なる「報告の場」ではなく、部下の成長と信頼関係を育むための時間として位置づけています。以下が主な目的です。
- 信頼関係の構築(部下の心理的安全性を高める)
- キャリア開発の支援
- 課題・悩みの早期把握
- 業務効率や優先順位の整理
- モチベーションの維持・向上
特に強調されているのが、「上司が話す場」ではなく「部下が主役」の対話時間であるという点です。
つまり、上司はファシリテーターとして「話を聞く」「問いかける」「引き出す」ことが求められます。
実際に行われている1on1の内容とは?
Googleの1on1の特徴は、「個人の話題にフォーカスし、対話の深さを追求している」点にあります。単なる業務の進捗確認にとどまらず、以下のような点に重きを置いています。
● 上司の役割は“コーチ”であり“相談相手”

Googleでは「マネージャーは答えを持っていなくてよい」という考えが浸透しています。その代わり、部下の話を丁寧に聞き、考えるヒントを提供する“コーチ”的な関わり方が求められています。
実際に使われているフレームワークには、以下のようなものがあります:
- GROWモデル:Goal(目標)→Reality(現状)→Options(選択肢)→Will(意志)
- 反復質問法:「なぜそう思ったの?」「他に方法は?」と掘り下げて思考を促す
● 会話の記録と透明性の確保

Googleでは、1on1の内容は基本的にドキュメントに残すことが奨励されています。これは次回以降の対話をスムーズにするためであり、かつ、部下のキャリア目標や悩みを忘れずに支援するための仕組みです。
一部のチームでは、Google DocsやNotionなどを使って、マネージャーと部下の間で「共有ノート」を作成し、相互に編集しながら継続的に対話を深めています。
Googleの1on1で使われる質問例
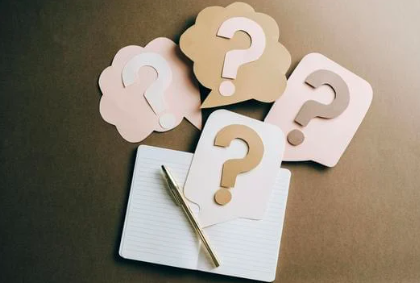
Googleでは、1on1での対話をより深めるために、マネージャーが使う「質問テンプレート」が共有されています。たとえば以下のような問いがよく用いられます。
- 今、最もやりがいを感じている仕事は何?
- 何か不安やプレッシャーを感じていることはある?
- チームの中で改善したいことはある?
- 自分の成長を感じられている?
- 私(上司)に対して改善してほしいことは?
これらの質問により、部下の本音や価値観を引き出し、より深い対話が可能になります。
1on1を機能させるGoogleの工夫
Googleでは、1on1が形だけのイベントに終わらないよう、組織全体でのサポート体制が整えられています。以下、その代表的な取り組みを紹介します。
● Oxygenプロジェクトとマネージャー育成
Googleは、2009年に実施した「プロジェクト・オキシジェン(Project Oxygen)」において、マネージャーの行動とチームの成果の相関関係を分析しました。そこで明らかになった“良いマネージャーに共通する8つの行動”の中には、1on1に直結するスキルが含まれていました:
- 良いコーチである
- チームのメンバーに権限を与える
- チームメンバーのキャリアに関心を持つ
- 聴くスキルが高い
これを受けて、Googleはすべてのマネージャーに対して1on1スキル研修を提供し、実施頻度や話す内容、傾聴の姿勢について標準化を進めています。
● “心理的安全性”を基盤とした文化的支援
Googleが大切にしているのは、「1on1のテクニック」ではなく「1on1が機能する土壌」です。その中心にあるのが、心理的安全性です。
1on1の場で部下が本音を語るには、「この人に話しても大丈夫」と感じられる信頼関係が必要です。Googleでは以下のような文化的支援が行われています:
- フィードバックの奨励:上司に対しても率直な意見を言ってよいという文化がある
- エラーやミスは責めない:問題は“個人”ではなく“仕組み”にあるとする姿勢
- 全員が発言できる場づくり:少数派・新参者も意見を述べやすい設計
この文化があるからこそ、1on1も「本音の対話」が可能になるのです。
● マネージャー同士の“ふりかえり”
Googleの一部の部門では、マネージャー同士が1on1の振り返り会を実施しています。実施後に「どんな気づきがあったか」「難しかった点は何か」を共有し合うことで、マネジメントスキルを高め合う仕組みです。
実際の現場エピソード:Google社内での1on1のリアル

Googleでは1on1が形式的な業務確認の場ではなく、「信頼に基づく対話の場」として機能しています。そのリアルな姿を、以下のような具体的なエピソードから見ていきましょう。
● エピソード①:上司が“キャリアパートナー”になった事例
あるプロダクトマネージャーは、入社当初から「自分は将来的にマネジメントに進むべきか、エンジニアとして専門性を深めるべきか」で悩んでいました。1on1では、その話題が何度も取り上げられ、マネージャーは次のようなアプローチをとりました。
- キャリアの方向性に関する本人の希望を聞き取る
- 社内のロールモデル(マネージャー職やスペシャリスト)を紹介
- 実際にその職種に近い業務を試す“小さなチャレンジ”を提案
この過程を通じて、当該社員は「やっぱり技術で貢献したい」という思いを再確認し、自信を持ってスペシャリストの道を選びました。
1on1の対話が、キャリア選択の迷いを整理するきっかけとなった典型例です。
● エピソード②:「沈黙」が生んだ信頼のきっかけ

別のチームでは、新しく着任したマネージャーが、口数の少ない若手メンバーとの1on1で「毎回10分以上、無言の時間が流れる」ことに悩んでいました。
しかし、そのマネージャーは無理に話題を作らず、静かに相手の反応を待ち続けました。数週間後、相手の方から「実はチームの方向性に不安がある」と口を開き、それをきっかけに関係が深まりました。
このケースでは、「沈黙を恐れない姿勢」が心理的安全性をつくるカギとなりました。Googleではこのような対話も、“成功した1on1”と捉えられています。
● エピソード③:チーム全体の課題が1on1で顕在化した事例
ある開発チームでは、複数のメンバーが1on1で「最近、開発スピードが落ちてきた」「レビューが形骸化している」といった声を上げていました。
マネージャーはこれらを記録し、共通項を整理した上で、全体会議で「皆が感じている課題」として共有。その後、レビュー体制を見直し、ツールの導入を決断しました。
このように、個人のつぶやきが、チーム改善の出発点になるというのも、Googleの1on1文化ならではの強みです。
● エピソード④:「フィードバック文化」が根付く背景
Googleでは、部下から上司へのフィードバックも1on1で行われます。
あるシニアエンジニアは、1on1の場で上司に「最近のフィードバックが曖昧で、何を改善すべきか分かりにくい」と率直に伝えました。マネージャーはそれを歓迎し、次回からは「この行動は良かった/改善点はここ」というように、より具体的なフィードバックを心がけるようになりました。
このように、「上司へのフィードバックが自然に行われる」のは、1on1が双方向で信頼ある場であることを象徴する事例です。
● 1on1は“雑談”も大事

Googleのあるチームでは、1on1の最初の5~10分は「雑談タイム」として確保されています。
- 最近見た映画
- 子どもの学校行事
- 趣味や旅行の話
一見、仕事に無関係なこの雑談が、「心の距離を近づける」「お互いを知る」ことにつながり、本題に入った際の心理的安全性を高めているのです。Googleはこうした“余白の時間”を非常に大切にしています。
● Google社員の声(一部翻訳引用)
「1on1は単に会話の場ではなく、“自分の声がちゃんと届いている”と感じられる大事な時間です」(ソフトウェアエンジニア)
「マネージャーが“答えをくれる”よりも、“一緒に考えてくれる”という姿勢の方がありがたいですね」(プロダクトマネージャー)
小さな会話が大きな信頼を生む
Googleの1on1のリアルな姿を見て分かるのは、「一つひとつの会話が、信頼・成長・チーム改善の原動力になっている」ということです。形式やルールではなく、“人と人との対話”として1on1を捉える姿勢が、Googleの強さを支えているのです。
よくある誤解と失敗例

1on1を導入しても、うまく機能しないケースもあります。Googleでは、以下のような「NGパターン」を注意喚起しています。
- 一方的に上司が話す
- 業務のチェックリストになってしまう
- フィードバックがなく「ただの雑談」になる
- 実施頻度が低く、信頼関係が築けない
- 部下の発言が無視され、改善に反映されない
Googleでは、1on1は「対話の質」が何より重要であると強調しています。
日本企業での応用と実践ポイント
日本企業でもGoogleの1on1を参考にした取り組みが進んでいます。ただし、日本の文化や働き方に合わせた工夫が必要です。
✅ ポイント①:心理的安全性の確保
日本人は本音を言いにくい傾向があるため、上司の「聴く姿勢」と「共感」が特に重要です。
✅ポイント②:目的の明確化
業務報告ではなく、「あなたのための時間」であることを毎回伝えましょう。
✅ポイント③:無理のない頻度で継続する
最初は月1回からでもOK。継続が信頼を生みます。
まとめ:1on1がもたらす組織の変化

Googleの1on1は、単なるマネジメント手法ではなく、「信頼を軸にした組織づくり」の基盤となっています。定期的な1on1を通じて、メンバーの本音を引き出し、課題を早期に察知し、個人の成長を支援する——これこそが、現代的なリーダーシップに求められる姿勢です。
日本でも「報告型」から「対話型」マネジメントへの移行が進む今、Googleの1on1から学ぶことは多いはずです。まずは小さく始めて、あなたの組織に合った1on1を育てていきましょう。