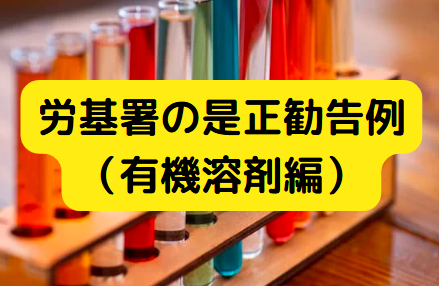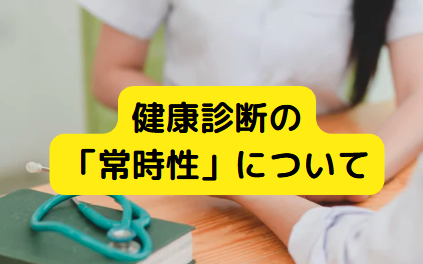
労働安全衛生法では、「常時従事する労働者に対して健康診断を実施する」など、多くの健康診断が「常時」という言葉とともに規定されています。しかし、ここでいう「常時」とは具体的にどのような意味なのでしょうか?
本記事では、労働安全衛生法における「常時性」の定義、適用範囲、注意点について詳しく解説します。
じん肺法、粉じん則の「常時性」について

昭和58年4月1日の事務連絡「じん肺法及び粉じん障害防止規則に係る常時の取り扱いについて」について参考に考えていきましょう。
昭和58年4月1日付事務連絡の内容
じん肺法及び粉じん障害防止規則に関する常時性の判断は、行政上の措置を行う場合に限り次に掲げる場合については常時性があるものとして取り扱うよう指示がでているようです。
- ほとんど毎日連続して粉じん作業に従事している場合
- 断続的かつ繰り返して粉じん作業を行う場合は、粉じん作業に従事する時間がおおむね1週間については3時間、1月については12時間を超えている場合。なお、作業時間が1月を超えた時間で繰り返される場合は1月を単位とした平均時間で判定をする。
- 臨時の粉塵作業(一期間をもって終了し、繰り返されない作業)に従事する場合で、その期間が3月を超える場合。
常時粉じん作業の事例
行政が過去に常時粉じん作業として取り扱った事例は次のとおりです。
- 毎日1時間程度工具類の研磨を行う場合
- 毎日2~3時間アーク溶接を行う場合
- 1日あたり2時間かつ1か月15日アーク溶接を行う場合
- 毎日1週間(約40時間)鋼製のタンク内で、手持ち式グラインダーを用いてさび落としを行う場合
- 毎日15日(1日あたり2時間)グラインダーにより鋳物のバリ取りを行う場合
- 鋳物業において所定労働時間および所定労働日数の大半を粉じん作業に従事する場合
- ガラス製造工場で毎日2時間以上原料の混合を行う場合
常時粉じん作業に該当しないとした事例
行政が過去に「常時」には該当しないとして事例は次のとおりです。
- 機械工場、鉄工場において、設備、機器の補修などのため、まれにアーク溶接を行う場合
- 鉄骨加工業などにおいて、月に2~3回、短時間、屋外のアーク溶接を行う場合
- 屋内て鉄骨の仮止めアーク溶接を1日あたり60か所行う場合
- 1日1時間、1か月2~3日はアーク溶接を行う場合
- 毎月15日(1日あたり10分間)グラインダーにより工具の研磨を行う場合
有機則、特化則などの「常時性」について

昭和50年代に東京労働局にて以下の指示がでているようです。
- 業務に継続的に従事する期間が3か月程度以上である場合
- 業務に反復継続的に従事する頻度が週1回以上である場合