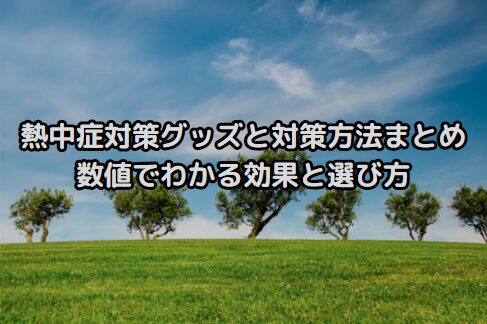健康診断の前日、何を食べたらいい?迷う方や社員に案内する担当者のための完全ガイドです。
健康診断は、私たちの健康状態を把握し、生活習慣病や重大な疾患の早期発見に役立つ重要な機会です。しかし、その精度を確保するには、検査前の過ごし方、とくに前日の食事内容が非常に大切です。特に血液検査、胃部検査(バリウム検査、内視鏡検査)、尿検査などは、直前の食事が結果に大きな影響を与えるため注意が必要です。
この記事では、健康診断を受ける本人に加え、企業や団体で健康診断を案内する担当者にも役立つ、前日の食事に関する医学的知識と具体的なメニュー例をご紹介します。
健康診断前日の食事が重要な理由
検査結果への影響

健康診断では、空腹時の血液検査や、胃部の状態を観察する検査が行われます。食事の内容や時間によっては、以下のような検査結果に影響を及ぼします。
- 血糖値や中性脂肪(トリグリセリド)の上昇:高脂質・高糖質の食事を摂ると、翌朝の空腹時でも数値が高く出てしまうことがあります。
- 肝機能数値の変動:脂肪分やアルコールの摂取で肝臓に負担がかかると、AST(GOT)・ALT(GPT)などの肝機能検査値に影響。
- 胃の検査が不正確になる:胃カメラやバリウム検査は、胃の中が空であることが前提。前夜に消化の悪いものを食べると残留物が検査の妨げになります。
医学的推奨事項
厚生労働省や健康保険組合が発行するガイドラインでは、健康診断前日の夜は「脂っこいものやアルコールを避け、午後9時以降は食事を控える」ことが一般的に推奨されています。
健康診断前日に避けたい食べ物・飲み物
前日の食事では、以下のような食品・飲料は避けるようにしましょう。
避けるべき食べ物
- 揚げ物(唐揚げ、天ぷら、とんかつなど)
- 脂肪の多い肉(霜降り肉、ベーコン、サラミ)
- スナック菓子やチョコレート
- 洋菓子(ケーキ、ドーナツなど)
- 香辛料の強いもの(カレー、麻婆豆腐)
避けるべき飲み物
- アルコール全般(ビール、日本酒、ワイン、焼酎など)
- 糖分の多い清涼飲料水(コーラ、スポーツドリンク)
- カフェインを多く含むコーヒー・エナジードリンク(寝つきに影響)

健康診断前日のおすすめ食事メニュー【例付き】

健康診断の前日は、消化に良く、低脂肪・低糖質であることが理想的です。以下に朝・昼・夕食のおすすめメニュー例を紹介します。
朝食(例)
- ごはん(お茶碗1杯)
- 温野菜のおひたし
- 焼き鮭(少量)
- 味噌汁(具は豆腐とわかめ)
昼食(例)
- うどん(つゆは薄め、具材はねぎ・卵など軽め)
- 小鉢にひじき煮や冷奴
夕食(例)※午後8時までに済ませる
- おかゆまたは白米(軽め)
- 湯豆腐(ポン酢少量)
- 茹でたブロッコリーやにんじんなどの温野菜
- 白身魚の煮つけ(少量)
就寝前
- 水分は水または白湯を摂取(カフェインレス)
- 午後9時以降は絶食(検査開始時間により異なるため案内を確認)
健康診断を案内する担当者が注意すべきポイント
企業の人事担当者や総務担当者が健康診断を案内する際には、次のような点に留意することが重要です。
明確な案内文を準備する
「健康診断前日の過ごし方」に関する案内を文書やメールで配布しましょう。以下のような情報を盛り込むと効果的です。
- 食事制限の開始時間(例:前日21時以降は食事NG)
- 禁止される食品・飲料の例
- 飲水可否(多くの血液検査では水分はOK)
- 服薬がある場合の対応(かかりつけ医に相談)
社員の理解を促す工夫
- ポスターや社内掲示板での告知
- 健診当日の持ち物チェックリスト
- メールでのリマインド送信
特別な配慮が必要なケース
- 妊娠中の社員
- 持病がある社員(糖尿病、心疾患など)
- 外国籍社員への多言語対応
よくある質問(Q&A)
- Q水は飲んでいいの?
- A
基本的に水や白湯は検査当日でも摂取して構いません。ただし、胃カメラ検査や腹部超音波検査がある場合は、事前に案内を確認しましょう。
- Q朝食を抜くのは絶対?
- A
血液検査などの空腹時検査がある場合、当日の朝食は絶対に抜いてください。どうしても空腹が辛い場合、水を少量飲んでしのぎましょう。
- Q前日の夜にアルコールを飲んだらどうなる?
- A
肝機能検査や中性脂肪値に悪影響を及ぼします。検査前日はアルコールの摂取は厳禁です。
まとめ:前日の食事で健康診断を成功に導こう
健康診断は健康維持と病気の早期発見のために欠かせない機会です。前日の食事は、検査結果の正確性に直結するため、軽視せず計画的に準備しましょう。特に脂肪分・糖分・アルコールを控え、消化の良い和食中心の食事を心がけることで、安心して健診を受けられます。
また、案内を行う担当者の方は、社員がスムーズに検査を受けられるよう明確で実用的な情報提供を心がけましょう。企業全体で健康意識を高め、健診の精度を高める取り組みが大切です。