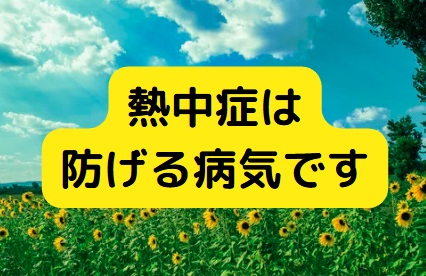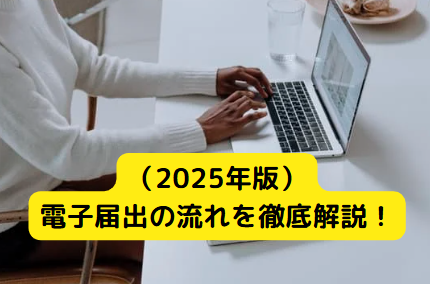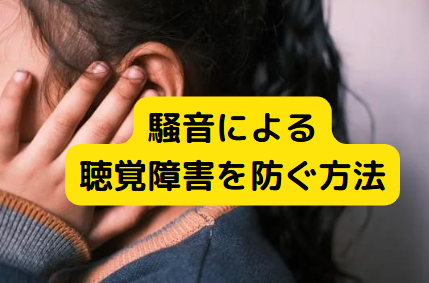
「職場の騒音がうるさいけど、耳への影響ってあるの?」
そんな疑問を持っている方へ。実は、85dB以上の騒音が続く職場では、騒音性難聴(そうおんせいなんちょう)と呼ばれる聴覚障害のリスクが高まります。
これは、長時間にわたって耳に大きな音が入ることで、徐々に聴力が低下していく障害で、一度失った聴力は基本的に回復しません。
2023年(令和5年)4月には、厚生労働省が「騒音障害防止のためのガイドライン」を30年ぶりに改訂。現場でのリスク管理や、耳を守るための対策が大きく見直されました。
本記事では、職場の騒音による聴覚障害の原因や症状、ガイドラインに基づいた最新の対策方法を、安全管理者の目線でわかりやすく解説します。
「騒音対策って何から始めればいいの?」「耳栓だけで本当に大丈夫?」といった疑問にもお応えしますので、職場の安全管理・健康管理に関わる方はぜひご一読ください。
騒音による聴覚障害とは?

「なんか最近、耳が遠くなったかも…?」
そんな声を耳にしたことはありませんか?それ、実は騒音による聴覚障害のはじまりかもしれません。
職場での騒音が原因となって発症する聴覚障害は「騒音性難聴」と呼ばれます。これは、長期間にわたり85dB以上の騒音にさらされることで、内耳の感覚細胞がダメージを受け、音が聞こえにくくなる状態です。
初期は「高い音が聞き取りづらい」「会話の一部が聞こえにくい」といった軽度の症状から始まり、徐々に進行します。そして一度失われた聴力は、基本的に回復しません。
どんな職場が危険?騒音レベルの目安

騒音は意外と身近な存在。以下のような職場では、常時騒音にさらされるリスクがあります。
- 建設現場(重機、削岩機)
- 製造工場(プレス機、コンプレッサー)
- 金属加工現場(溶接、グラインダー)
- 運輸・物流(エンジン音、荷下ろしの衝撃音)
騒音レベルの目安(dB)
| 音の種類 | dB(デシベル) | 危険度 |
| 普通の会話 | 約60dB | 問題なし |
| 掃除機、騒がしい街 | 約85dB | 長時間でリスク発生 |
| 工事現場の重機 | 約100dB | 数分でリスクあり |
| ジェット機のエンジン近く | 約120dB | 即時に危険 |
放置するとどうなる?聴覚障害のリスク
騒音性難聴を放っておくと、日常生活にもさまざまな支障が出てきます。
- 会話が聞き取れず、コミュニケーションにストレス
- 周囲の音が分からず、事故や危険を察知しづらくなる
- 孤立感、抑うつ、集中力の低下といった精神的負担
しかも、これらは徐々に進行するため、本人も気づきにくいのが厄介なところです。
令和5年改訂のガイドラインのポイント

厚生労働省は2023年4月、約30年ぶりに「騒音障害防止のためのガイドライン」を改訂しました。これには、現代の働き方や新しい測定技術に対応する内容が盛り込まれています。
主なポイントは以下の4つです:
(1)騒音障害防止対策の「管理者」の選任
事業場ごとに対策を管理・推進する責任者を明確にしましょうという内容です。誰が責任を持って騒音対策を実施するのかを明確にすることで、職場全体での取り組みが強化されます。
(2)個人ばく露測定の導入
従来の「作業場の平均的な音の大きさ(定点測定)」ではなく、作業者ごとの実際のばく露レベル(個人ばく露)を測る方法が推奨されています。これにより、本当にリスクがある人を把握できるようになります。
(3)聴覚保護具の適正な選定
「とりあえず耳栓つけとけ」ではなく、騒音レベルや作業内容に応じた最適な保護具の選定が必要です。耳栓、イヤーマフなどをフィットテストで適切に装着できているか確認することも求められます。
(4)健康診断項目の見直し
聴覚検査に関して、4000Hzの高周波数の聴力測定を導入することが明記されました。これは、騒音性難聴が最初に影響を及ぼす周波数帯で、早期発見に有効です。
職場で実践すべき騒音対策
では、実際にどんな対策ができるのか?ここでは現場で実践しやすい対策をいくつか紹介します。
✅ 個人でできる対策
- 騒音ばく露の高い作業時には耳栓やイヤーマフを着用
- 定期的に聴力検査を受ける
- 作業終了後も耳の違和感をメモに残す

✅組織としてできる対策
- 騒音源の機械を静音タイプに変更
- 吸音材の設置や機械の囲い込みで音を減らす
- 作業者のローテーションによってばく露時間を減らす
- 騒音レベル測定と記録の定期実施

法令と基準を再確認
- 労働安全衛生法では、85dBを超える環境では「聴力検査の実施」が義務付けられています。
- 騒音レベルの測定、耳栓の提供など、事業者にはさまざまな管理責任があります。
- 改訂ガイドラインを参考に、安全衛生委員会などで定期的に見直しを行いましょう。
まとめ:耳を守ることは働き続ける力を守ること

騒音性難聴は、気づきにくく、そして一度進行すると取り戻すことができません。
でも、令和5年のガイドラインを活用し、正しく測定し、適切に保護すれば、防ぐことは可能です。
耳を守ることは、未来の働き方を守ること。
あなた自身と、職場の仲間のためにも、今できることから始めていきましょう!