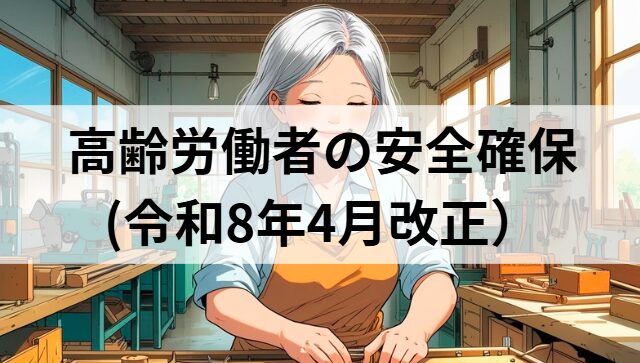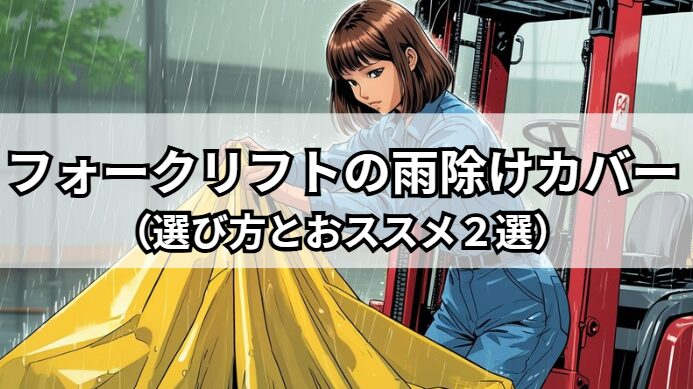現場で働く作業員や安全衛生担当者にとって、複数の技能講習修了証の管理は大きな負担です。フォークリフト、玉掛け、クレーン、足場、高所作業車など、作業内容ごとに発行される修了証を1枚にまとめて管理できたら…と感じたことはありませんか?
実は近年、技能講習の修了証を“1枚のカード”にまとめる取り組みが進んでいます。これは安全管理を効率化するだけでなく、本人証明や現場入場の迅速化にもつながります。
本記事では、技能講習修了証をまとめる最新の方法、法的な注意点や申請手順について、わかりやすくまとめました。
2025年現在の最新情報に基づいた完全ガイドです。
技能講習修了証とは?なぜ複数持つ必要があるのか
建設現場や工場では、労働安全衛生法に基づいて作業ごとに技能講習の修了が義務付けられています。
たとえば、以下のような講習があります
- フォークリフト運転技能講習
- 玉掛け技能講習
- 小型移動式クレーン技能講習
- 足場の組立て等作業主任者技能講習
- 高所作業車運転技能講習
これらはすべて、法令で義務づけられている資格であり、それぞれの修了証が発行されます。
結果として、1人の作業員が複数の資格証を所持して現場に出ることが当たり前になっていますが、これが紛失・更新・提示の面で非効率な状態を生んでいます。
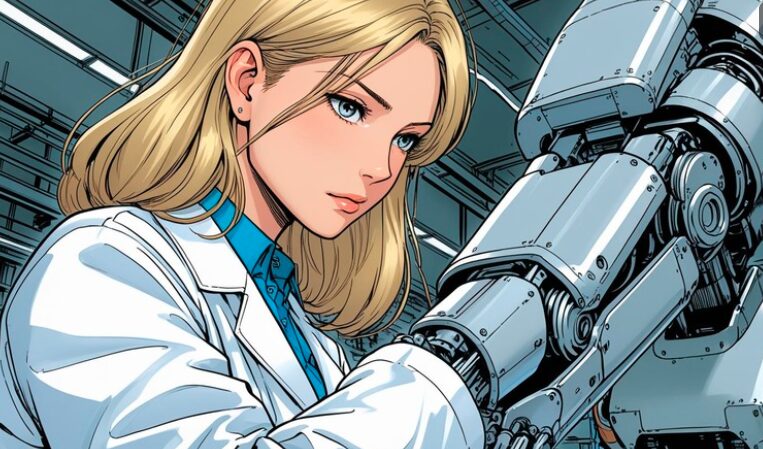
技能講習をまとめるとは?その背景とニーズ
「まとめる」とは、これらバラバラの技能講習修了証を1枚のカードで一元管理することを意味します。
背景には以下のような現場の課題があります
- 修了証が紙製で破損・紛失しやすい
- 講習先ごとに発行様式が異なり、確認が煩雑
- 労務管理や現場入場チェックに時間がかかる
- 複数の講習を受ける人が常に複数枚を携帯する必要がある
このような課題を解決するため、厚生労働省では「統合カード」の発行を推奨しています。
技能講習修了証を1枚のカードにまとめる方法
厚生労働省は、技能講習を受講したすべての労働者の資格情報を一元管理するデータベースを構築し、発行事務局が「技能講習修了証明書(統合カード)」を交付しています。

これは、労働安全衛生法第61条第3項に規定された「資格を証する書面」の携帯義務を保持しつつ、複数の紙原本を1枚に集約する仕組みです
統合カードと紙の修了証(原本)の違い
- 修了証(原本)は、各登録教習機関が発行する正式な証明書で、法的保持義務があり、滅失・氏名変更時には再発行が求められます
- 統合カードは発行事務局がデータベースから作成するICカードで、複数資格を1枚にまとめて携帯できる。ただし原本の保持は依然必要です。

統合カードによって1枚にまとめた場合でも、原本の修了証は保管しておく必要があるよ。修了証は手元に持っている必要はないことがポイントだね!
統合できる技能講習と対象外のケース
統合できる講習
発行事務局データベースに登録された技能講習の修了履歴が対象で、フォークリフト・玉掛け・クレーン等の主要講習が含まれます
対象外
- 特別教育や安全衛生教育、免許等は統合カードでは証明不可です
- 講習機関から情報提供のない場合、統合カードは発行されません
手続きフローと必要書類一覧

主な手続きパターン
- 新規交付(当該カード未所持者)
- 再交付(紛失・損傷・氏名変更)
- 追加登録(既存カードへの講習追加)
必要書類(新規/再交付/追加に応じて)
| 必要書類 | 説明 |
|---|---|
| ①交付申込書 | 所定フォーム |
| ②証明写真 | 4.5×3.5cm、無背景 |
| ③本人確認 | 運転免許証等 |
| ④修了証複写/カード複写 | 新規・追加の講習分 |
| ⑤戸籍等 | 氏名変更時のみ |
申請方法別の注意点
- オンライン申請:6時〜24時対応。複数一括申込には非対応
- 郵送申請:返信用封筒に簡易書留404円分切手を貼付。
- 窓口申請:代理人、一括申込も可能。必要書類の確認に時間がかかる場合あり
料金・交付までの期間・再発行・追加登録
- 申請受付〜交付:通常約3週間
- 手数料:資格数に応じ変動。カード統合時の目安は1,500円前後(※詳細目安は案内に記載)
- 再発行・追加登録:紛失・氏名変更・講習追加の場合にも対応
利用メリットと導入時の留意点
◎ メリット
- 複数修了証を1枚に一本化して携帯負担軽減
- 損失・破損リスクを低減
- 官公庁・企業での点検対応にも効力発揮
× 注意点
- 原本+カードの二重管理が必要
- データベースに無い講習は統合対象外
- 特別教育は非対応で別途管理が必要
よくある誤解とQ&A
- 「統合カードは法律上の証明書と同等?」 → はい、労働安全衛生法上の携帯義務を満たす第一証明として認められますが、原本の保持義務は残ります
- 「他所講習はまとめられる?」 → 講習機関が異なっても、発行事務局の記録があれば可能です。記録漏れのない講習は追加登録で対応
- 「特別教育もまとめたい」 → 現状では不可。混合管理したい場合は教育手帳等別管理が必要です
まとめ:効率化と安全確保のトレードオフを越えて
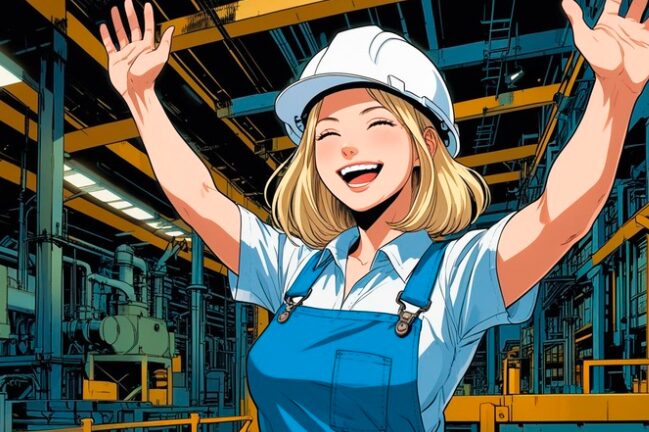
1枚の統合カードは、現場の負担軽減・迅速な資格確認・管理コストの削減に直結します。制度の法的位置づけが明瞭でありながら、原本保持・特別教育非対応などの管理の併行運用が現実なのも事実です。
まずは、発行事務局のデータベース登録状況を確認し、紛失・再交付・氏名変更・講習追加のニーズを整理していきましょう。これにより、安全管理の効率と柔軟性を両立した次世代の現場運営が実現できます。