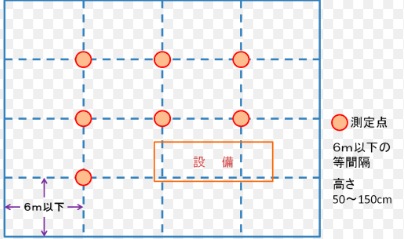冬季における除雪作業は、交通の安全を確保するために欠かせないものですが、除雪車の運行にはリスクが伴います。
本記事では、除雪車の安全対策に焦点を当て、運転手や周囲の人々が安全に作業を行うためのポイントを解説します。除雪車の運行に関する知識を深め、事故を未然に防ぐための情報を提供します。
除雪車とは?その役割と重要性
除雪車とは、積雪地域で道路や駐車場の雪を除去し、交通の安全と円滑な通行を確保するための特殊車両です。主にロータリー除雪車、プラウ除雪車、グレーダーなどがあり、用途に応じて使い分けられます。
除雪作業は、交通事故や渋滞の防止に加え、歩行者の安全確保や経済活動の維持にも重要な役割を果たします。しかし、作業中の視界不良やスリップ事故、機械トラブルなどのリスクが伴うため、安全対策が不可欠です。
除雪車の安全衛生法やその他の法令での位置づけ
労働安全衛生法
除雪車は、労働安全衛生法(安衛法)において「車両系荷役運搬機械」に分類されるため、安全管理が求められます。特に、公道や事業所内での使用において、作業者の安全を確保するためのルールが適用されます。
- 第28条(事業者の安全配慮義務):作業者の安全確保のため、適切な指導や対策を実施する必要があります。
- 第59条(安全教育):除雪車の運転業務を行う作業者には、必要な安全教育を実施することが義務付けられています。
道路交通法
- 除雪車は特種用途自動車として分類され、公道での走行には道路交通法の規制を受けます。
作業機械の安全基準(厚生労働省指針)
- 除雪作業における安全管理基準が示されており、定期点検・整備、適切な防寒対策、合図確認などが求められます。
また、自治体によっては、独自の安全基準や運用ルールが定められている場合もあるため、使用する地域の規定を確認することが重要です。
除雪車を運転するために必要な資格

公道を走行する場合(道路交通法)に必要な資格
✅ 大型特殊免許(第一種運転免許)
- 除雪車は「大型特殊自動車」に分類されるため、公道を走行する場合は大型特殊免許が必要です。
事業所・作業現場内で運転する場合(労働安全衛生法)
✅ 車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削)運転技能講習
- 除雪作業に使われるホイールローダー型除雪車は、「車両系建設機械」に分類されるため、技能講習を受講する必要があります。
作業環境や車両の種類によって必要な資格が異なるため、事前に確認し、適切な資格を取得したうえで運転することが重要です。
除雪車の安全対策の必要性
除雪車の運転には視界不良・スリップ・接触事故などのリスクが伴うため、安全対策が不可欠です。冬季の作業環境は悪天候や積雪による滑りやすい路面が多く、適切な対策を怠ると重大事故につながる可能性があります。
【安全対策のポイント】
✅ 事前点検の実施:ブレーキ・ライト・ワイパーなどの機能確認
✅ 視界確保:曇り止め・ライト点灯・ミラー調整
✅ 適切な速度管理:急加速・急停止を避ける
✅ 周囲の安全確認:歩行者や他の車両との接触防止
また、十分な休息と適切な防寒対策を行い、運転者の集中力を維持することも重要です。
適切な安全対策を講じることで、作業者自身や周囲の人々の安全を確保し、スムーズな除雪作業を実現できます。
除雪車運転手の安全教育

除雪車の安全教育では、安全運転の基本、作業環境のリスク、緊急時の対応などを行います。
主な内容は以下の通りです。
✅ 機械の構造・操作方法の理解
- 除雪車の種類や機能、適切な操作手順を学ぶ。
✅ 安全運転技術
- 悪天候・視界不良時の運転方法、スリップ防止策、適切な速度管理。
✅ 周囲の安全確認
- 歩行者や他車両との接触防止、死角確認の重要性。
✅ 点検・メンテナンス
- 始業前点検の実施、ブレーキ・ライト・ワイパーの確認。
✅ 緊急時の対応
- 故障・事故発生時の対応手順、連絡体制の確認。
適切な安全教育を受けることで、事故を防ぎ、安全な作業環境を確保できます。
定期的なトレーニング
除雪車の運転には高度な操作技術と安全意識が求められるため、定期的なトレーニングが不可欠です。経験者でも技術の維持・向上や最新の安全対策の習得が必要となります。
✅ 操作技術の維持・向上
- 除雪車の正確な操縦、狭い場所での除雪技術、緊急時の対応を実践。
✅ 安全運転の再確認
- スリップ防止策、悪天候時の視界確保、速度管理などの実地訓練。
✅ 機械の点検・メンテナンス訓練
- 始業前点検の実施、トラブル時の対応手順を確認。
✅ 実地訓練の実施
- 降雪前にシミュレーション訓練を行い、現場での実践力を強化。
定期的なトレーニングを実施することで、安全性を高め、事故のリスクを最小限に抑えることができます。
除雪車の運行前チェックリスト

機械の点検
- エンジン・バッテリー:正常に始動するか確認
- 燃料・オイル・冷却水:十分な量があるかチェック
- ブレーキ・ライト・ワイパー:作動状態を確認
- ミラー・カメラ:視界確保のため調整
- ブレード・ロータリー:正常に動くか試運転
- 油圧・可動部:異音や動作不良がないか確認
燃料とオイルの確認
- 残量チェック:燃料タンクのメーターや目視で十分な燃料があるか確認。
- 寒冷地仕様の燃料使用:冬季は軽油の凍結を防ぐため、寒冷地仕様の燃料を使用。
- 水抜きの実施:タンク内の水分が凍結しないよう定期的に水抜きを行う。
- エンジンオイル:適正な油量・粘度・汚れの有無を点検。汚れがひどい場合は交換。
- 油圧オイル:ロータリーやブレードがスムーズに動くよう、油圧オイルの量や漏れをチェック。
- ギアオイル・ブレーキオイル:適正レベルを維持し、異常があれば補充または交換。
緊急時対応の準備
- 無線・携帯電話の確認
- 緊急連絡先の把握
除雪作業中の安全対策
作業エリアの周知
除雪作業を安全に行うためには、作業エリアの周知と立ち入り禁止措置が重要です。
事前に作業区域を明確にし、看板・カラーコーン・警告灯などを設置して、歩行者や他の車両が誤って進入しないようにします。
また、作業開始前に関係者へ周知し、無線や合図で連携を取ることで、予期せぬ事故を防ぐことができます。特に、早朝や夜間作業では視認性を高めるためのライトや反射材の活用が効果的です。
他車両との距離を保つ
除雪作業中は後続車や対向車との適切な距離を保つことが重要です。
除雪車は一般車両よりも低速で走行し、急な方向転換や後退を行う場合があるため、周囲の車両と十分な間隔を確保する必要があります。
また、吹き飛ばされた雪や氷塊が他車両に影響を与える可能性があるため、安全な距離を維持しつつ、周囲の動きを常に確認することが事故防止につながります。
緊急時の対応策

除雪車の安全対策において、特に「緊急時の対応策」は重要です。事故発生時に適切な行動を取ることと、緊急連絡先を確認しておくことは、迅速な対応と安全の確保に繋がります。
事故発生時の行動
除雪車の運転中に事故が発生した場合、冷静に行動することが求められます。以下の手順を踏むことが基本です。
- 安全確認
事故が発生した場合、まずは自車および周囲の安全を確認します。車両が停車した場所が交通の妨げにならないよう、安全な場所に移動させることができれば移動します。移動が不可能な場合は、事故車両に対する注意喚起のため、三角表示板や警告灯を点灯させることが重要です。 - 負傷者の確認
自分自身や同乗者、その他の関係者に怪我がないかを確認し、負傷者がいる場合は即座に応急処置を行い、必要であれば救急車を呼ぶ必要があります。 - 事故の報告
事故発生時には、すぐに上司や所属部署に報告し、現場の状況を伝えます。その後、警察への連絡を行い、事故の証拠を収集します(写真撮影など)。 - 事故処理
事故車両の修理や撤去の手配を行います。作業中は交通の安全を確保するため、周囲に十分な注意を払いながら作業を進めます。
緊急連絡先の確認
除雪車運転者は、緊急時に迅速に対応できるように、常に緊急連絡先を確認しておくことが必要です。これには、以下の連絡先が含まれます。
- 緊急サービス
警察や消防、救急車の連絡先は必ず把握しておくべきです。特に冬季には天候や道路状況が悪化する可能性があるため、事故発生時には迅速に連絡することが重要です。 - 所属部署や上司の連絡先
事故が発生した場合、速やかに上司や管理者に報告する必要があります。緊急時の対応として、作業現場での指示を受けるためにも、連絡先は必ず確認し、すぐにアクセスできる状態にしておきます。 - 同僚や連絡網
事故の状況によっては、他の除雪車や作業員と連携して対応することもあります。作業現場で協力を得るためにも、同僚や他の関係者の連絡先を事前に把握しておくことが有効です。
これらの緊急連絡先は、万一の事故や緊急時に適切な対応ができるよう、日頃から確認し、常に連絡先リストを最新の状態に保っておくことが求められます。
事故発生時に適切に行動し、迅速に連絡を取ることで、被害の拡大を防ぎ、早期の対応が可能となります。