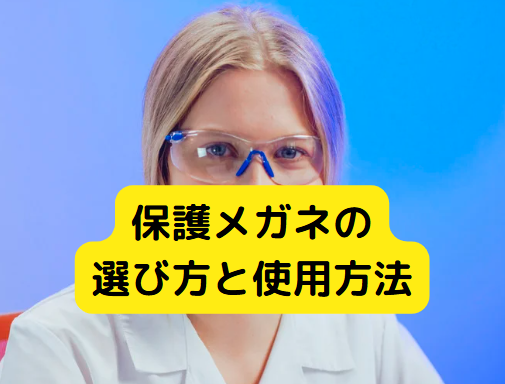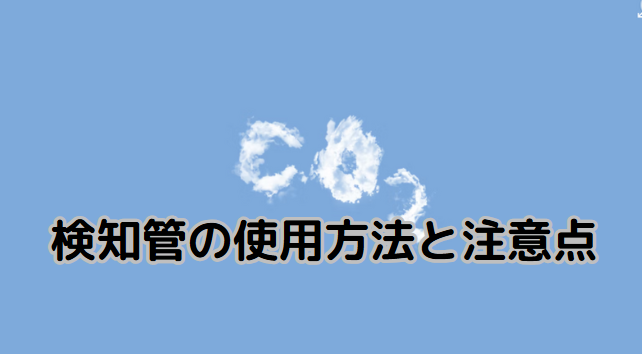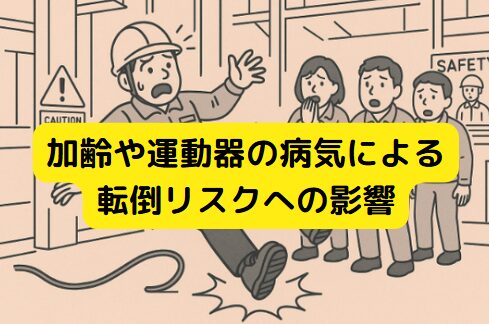
転倒による労働災害は、建設業や製造業はもちろん、オフィス業務など多くの職場で発生しています。床の段差や滑りやすい床材といった「外的要因」に注目されがちですが、実は「内的要因」も見過ごせません。特に中高年齢層の労働者が多い現場では、加齢による身体機能の低下や運動器疾患(ロコモ)などが転倒リスクを高める要因となります。
本記事では、転倒における内的要因を中心に、労働災害の予防に活かせる知識をわかりやすく解説します。
転倒の内的要因とは?
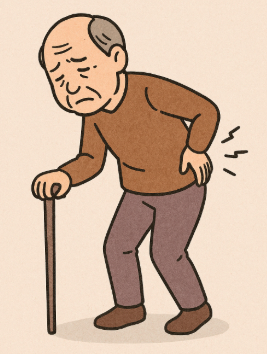
転倒を引き起こす要因は「外的要因(環境に起因するもの)」と「内的要因(個人の身体的・心理的状態によるもの)」に分けられます。
たとえば、内的要因には以下のようなものがあります。
- 加齢に伴う筋力やバランス能力の低下
- 神経・感覚系の機能低下
- 運動器疾患(ロコモティブシンドローム含む)
- 慢性疾患(高血圧・糖尿病など)による一時的なふらつき
- 一部の薬剤の副作用(めまい、眠気)
これらは、作業者自身の体調や体の状態に由来するため、個人差が大きく、見た目には気付きにくいという特徴があります。安全対策では、外的環境の整備だけでなく、従業員一人ひとりの健康状態や身体的変化にも目を向ける必要があります。
加齢による影響と転倒リスクへの影響
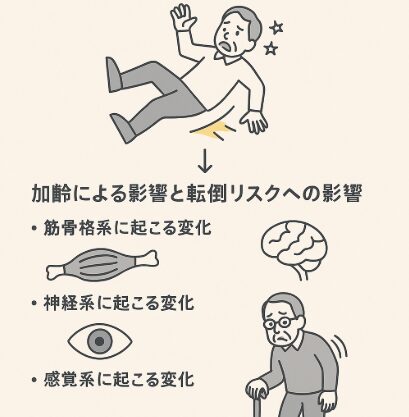
高齢化が進む中で、現場には60代以上の労働者も多く従事しています。こうした年齢層の方々にとって、「転倒」はもっとも身近で、かつ重症化しやすい労働災害のひとつです。転倒リスクの背景には、加齢によって生じる身体機能の低下があります。
加齢と筋骨格系の変化
加齢とともに、筋肉量や筋力は徐々に減少します。特に脚部の筋力が低下すると、立ち上がりや階段昇降、踏ん張りといった日常的な動作が不安定になりやすくなります。
サルコペニア(筋肉の減少)
サルコペニアとは、加齢により筋肉量や筋力が減少する状態を指します。特に大腿四頭筋(太ももの前面)や下腿三頭筋(ふくらはぎ)といった、歩行やバランス保持に不可欠な筋肉が衰えると、ちょっとした段差でつまずいたり、立ち直り動作が間に合わなくなります。
姿勢保持筋の弱体化
腹筋や背筋といった姿勢を支える筋肉が弱ると、立位や歩行時に上半身が前傾しやすくなり、視野が狭まり、足元の障害物に気づきにくくなります。このため、作業現場では床のちょっとした段差や工具類へのつまずきが多発します。
神経系の変化と反応速度の低下
加齢に伴って、神経伝達のスピードが遅くなります。これは転倒リスクに直結する要素です。
反射時間の延長
たとえば、足が滑ったり、体が傾いたときに咄嗟に体勢を立て直す「反射動作」が遅れることで、転倒を防げなくなります。20代の若者なら即座に足を出してバランスを取れる場面でも、高齢者ではその一歩が遅れ、倒れ込んでしまうのです。
二重課題(デュアルタスク)の困難さ
歩行しながら会話をする、周囲に注意を払いながら作業をする、といった「複数のことを同時に行う」能力が落ちていくのも特徴です。これは作業現場では非常に重要なスキルであり、声をかけられた瞬間に注意が散漫になって足を踏み外す、という事故も見られます。
感覚系の変化とリスク認知の低下

視覚、聴覚、前庭感覚(バランス感覚)といった感覚系の衰えも、転倒に直結します。
視力の低下
加齢により、視力そのものだけでなく、暗い場所での視認能力(暗順応)や、奥行きの把握能力も低下します。床の傾斜や段差、滑りやすい箇所が認識できず、危険に気づくのが遅れるのです。
聴力の低下
周囲の音に気づきにくくなると、背後からの車両や他者の接近に気づかず、不意の驚きや回避行動が間に合わなくなります。また、声かけによる危険予知も届きづらくなるため、安全確認が成立しにくくなります。
前庭機能の低下
体のバランスを保つ内耳の機能が衰えると、わずかな揺れや傾きに対する補正が難しくなります。とくに振動の多い現場や足場が不安定な場所では、その影響が顕著になります。
歩行パターンの変化と“フレイル歩行”

加齢が進むと、筋力や関節の可動域の減少により歩行パターンにも顕著な変化が見られます。
特徴的な変化:
- 歩幅が狭く、すり足になる
- 歩行速度が遅くなる
- 上体が前傾し、足元しか見えない
- 転びそうになっても、とっさに足が出ない
こうした「フレイル歩行」の状態では、転倒の危険が非常に高くなります。特に床に置かれたケーブル、マットの端、ちょっとした段差といった“何でもない物”が転倒の原因になります。
加齢による内的要因の複合化
ここまで見てきた通り、加齢による転倒リスクは単一の要因ではなく、筋力・感覚・神経系など複数の機能低下が重なり合うことで大きなリスクになることがわかります。
たとえば「視力が低下+バランス感覚が低下+反射速度の低下」が重なると、わずかな床の濡れでも、
- 濡れていることに気づけない
- 滑っても踏ん張れない
- 体勢が崩れても支えられない
といった形で、転倒が避けられなくなります。
高齢労働者のための予防的アプローチ

加齢による身体の変化は避けられませんが、職場でできることはたくさんあります。
健康チェックと機能測定
- 年1回の定期健康診断に加えて、簡易的な歩行テストやバランステストを実施し、機能低下の早期把握を行う。
環境面の配慮
- 滑り止め床材の導入、照明の明るさの確保、段差の解消。
- よく通る場所に手すりを設置し、支持できるポイントを増やす。
教育・意識づけ
- 「年を取ると足元の感覚が鈍くなる」という知識を共有し、無理な動作を避ける意識を促す。
- 転倒事例の共有や、ヒヤリハットの振り返りを定期的に行う。
運動の促進
- 作業前のラジオ体操、下肢筋力を意識した軽運動の導入。
- 通勤時のウォーキングを推奨するなど、日常生活での運動機会の確保。

運動器の病気とロコモ
「ロコモティブシンドローム(ロコモ)」とは、加齢や病気によって筋肉・関節・骨などの運動器が衰え、移動能力が低下する状態を指します。ロコモは高齢者だけでなく、若年層でも生活習慣や運動不足によって発症することがあるため、全世代にとって注意が必要です。
ロコモの主な原因
- 変形性膝関節症、腰椎症などの慢性疾患
- 骨粗しょう症
- 筋力低下(サルコペニア)
- 脊柱管狭窄症や椎間板ヘルニア
ロコモによる影響
ロコモになると歩行速度が遅くなり、バランスを崩しやすくなります。また、痛みや関節のこわばりがあることで、「動きたくない」「休んでいたい」という心理的な萎縮が起こり、さらに身体機能が低下する悪循環に陥ります。
ロコモ対策としての職場での取り組み例
- 簡易的なロコモチェックの実施(片足立ちテスト、立ち座りテストなど)
- ストレッチ体操の導入(朝礼時や休憩前の軽い運動)
- 作業内容と身体機能に応じた配置転換
- 転倒リスクが高い作業者への見守りや声かけ
まとめ
転倒災害は環境要因に目が向きがちですが、実は加齢や健康状態などの「内的要因」も大きく関係しています。筋力・神経・感覚機能の低下、ロコモの進行などは、見た目ではわかりにくい分、発見が遅れやすく、重大な事故につながるリスクがあります。
職場では、身体の変化に気付けるような日々の健康チェックや運動習慣づくり、ロコモ対策の啓発が不可欠です。安全衛生担当者は、外的要因の整備とあわせて、従業員一人ひとりの健康状態を尊重したアプローチを進めることで、転倒災害を効果的に防止できるでしょう。