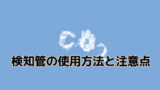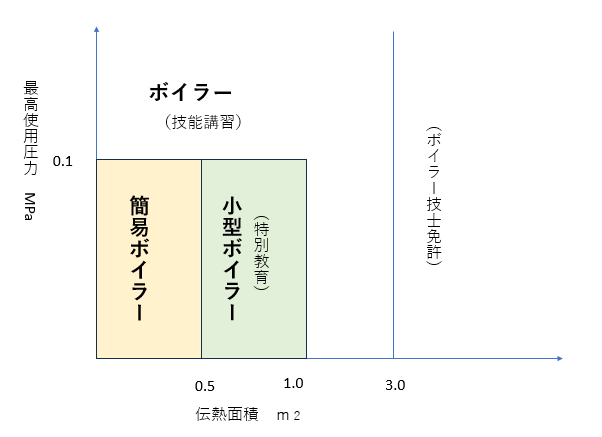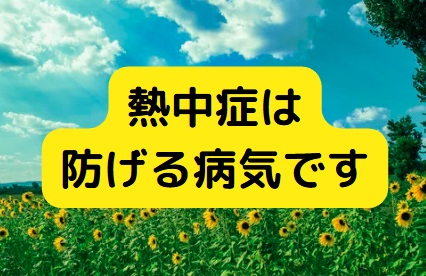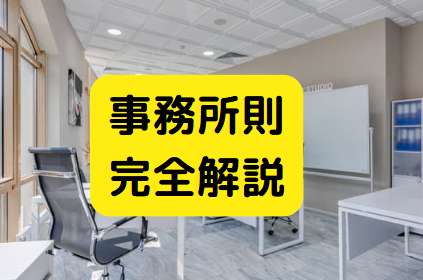
事務所の環境は、従業員の健康や業務効率に大きく影響します。
日本では「事務所衛生基準規則」によって、労働者が安全かつ快適に働ける環境を整えることが義務付けられています。
本記事では、事務所衛生基準規則の概要や具体的な対策、企業が守るべきポイントについて詳しく解説します。適切な職場環境を整え、従業員の健康と生産性を向上させましょう。
事務所則の適用範囲
建築基準法第2条第1号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作楽を含む。)に従事する労働者が主として使用する空間が、事務所則が適用になる「事務所」です。
事務作業には、一般的な事務作業、事務用機器を用いて行う作業のほか、帳簿の受付、文書の選別なども含まれます。
事務室の環境管理
第2条(気積)
作業者1人当たり10㎡以上の空間を確保する必要があります。(設備の占める容積、高さ4mを超える空間を除き、計算すること。)
【具体的な計算方法】
S=(V-v)/N
S: 労働者ひとり当たりの気積(m3)
V: 床面から4m以下の高さにある室の容積(m3)
v: 室にある設備の占める容積(m3)
N: 実際の室定員数(人)
第3条第1項(窓その他の開口部)
最大開放部分の面積が床面積の1/20以上とする必要があります。(1/20未満のとき換気設備を設けること。)
(参考)換気設備とは:換気筒、排気筒にような動力によらない換気設備、換気扇のような動力による換気設備および空気調和設備があります。(行政通達より)
第3条第2項(室内空気の環境基準)
一酸化炭素 50ppm以下、二酸化炭素 5,000ppm(0.5%) 以下でないといけません。
第4条(温度)

10℃以下のとき暖房等の措置、冷房実施のとき外気温より著しく低くしないといけません。
第5条第1項(供給空気の清浄度(空気調和設備と機械換気設備の場合に適用)
以下の環境とする必要があります。
- 浮遊粉じん 0.15mg/㎡以下とすること。
- 一酸化炭素10ppm以下、二酸化炭素1,000ppm以下であること。
- ホルムアルデヒド 0.1mg/㎡以下であること。
第5条第2項、第3項(室内空気の基準気流)
以下の環境とする必要があります。
- 0.5m/s以下とすること。(空気調和設備と機械換気設備の場合に適用)
- 18℃以上28℃以下、相対湿度が40%以上70%以下となるよう努めること。(空気調和設備の場合に適用)
(参考)室の気温と湿度は努力目標値を定めたもの。個々の部屋については、季節、作業状態を考慮して適切な範囲を決めて管理することが必要です。(行政通達より)
第6条測定(燃焼器具)

以下の環境とする必要があります。
- 排気筒、換気扇、その他換気の設備を設けること。
- 燃焼器具の異常の有無の日常点検を行うこと。
- 一酸化炭素 50ppm以下、二酸化炭素 5000ppm以下であること。
(参考)燃焼器具とは:湯沸器、石油ストーブ、ガスコンロなど燃料を利用する器具をいう(行政通達より)
第7条測定(中央管理方式の空気調和設備に適用)
室温、外気温、湿度、一酸化炭素、二酸化炭素について2月以内ごとに1回、定期に測定を行う必要があります。
ただし、室温、外気温及び湿度については、1年間、基準を満たし、かつ今後1年間もその状況が継続すると見込まれる場合は、春(3-5月)又は秋(9~11月)、夏 6~8月)、冬(12月~2月)の年3回の測定とすることができます。
測定の方法は次の方法により行うこととなっています。

| 測定事項 | 測定器 |
| 浮遊粉じん量 | グラスファイバーろ紙を装着した測定器 |
| 一酸化炭素 | 検知管 |
| 二酸化炭素 | 検知管 |
| 気温 | 0.5度目盛の乾湿球の湿度系 |
| 相対湿度 | 0.5度目盛の乾湿球の湿度計 |
| 気流 | 0.2メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計 |
| ホルムアルデヒド | 2.4ージニトロフェニルヒドラジン補修 |
第7条の2(ホルムアルデヒド)
窓の建築、大規模の修繕、大規模の模様替を行った場合は、当該室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回、測定する必要があります。
第9条(機械による換気のための設備の点検)
はじめて使用するとき、分解して改造、修理の際及び2月以内ごとに1回定期に行う必要があります。
第9条の2(空気調和設備)
(1)冷却塔
- 水質を水道法第4条に規定する水質基準に適合させること。
- 使用開始時,使用を開始した後、1月以内ごとに1回定期に点検すること。
- 1年以内ごとに1回定期に清掃すること。
(2)加湿装置
- 水質を水道法第4条に規定する水質基準に適合させること。
- 使用開始時、使用を開始した後、上月以内ごとに1回定期に点検すること。
- 1年以内ごとに1回定期に清掃すること。
(3)空気調和設備の排水受
- 使用開始時、使用を開始した後、1月以内ごとに1回定期に点検すること。
第10条(採光・照明)

(1)照度
- 一般的な事務作業 300ルクス以上
- 付随的な事務作業 150ルクス以上
(2)採光・照明の方法
明暗の対照とまぶしさを少なくする必要があります。
(参考)まぶしさを少なくする方法とは:目と光源を結ぶ線と視線とのなす角度が30度以上になるように光源の位置を定めることをいいます。
(3)照度設備の点検
6月以内ごとに1回定期に行う必要があります。
点検内容は、電球、反射笠などの汚れ、破損または機能劣化の確認を言います。
清潔
第13条(水質基準)
水質が水道法第4条に規定する水質基準に合格するレベルであることが必要です。
【給水栓における水にふくまれる残留塩素】
- 通常においては、遊離残留塩素の場合、0.1ppm以上、結合残留塩素の場合、0.4ppm以上とすること
- 汚染などにおいては、遊離残留塩素の場合、0.2ppm以上、結合残留塩素の場合、1.5ppm以上とすること。
第14条(排水設備)
汚水の露出防止のための補修及びそうじを行うこと
第15条
- 6月以内ごとに1回 、定期に、統一的に大掃除を行うこと.
- ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所、侵入経路、被害状況の調査を4月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと。
- 殺そ剤 、殺虫剤は、薬事法の承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
第17条(便所)

- 男性用と女性用に分けること。
- 男性用大便所は60人以内ごとに1個とすること。
- 男性用小便所は30人以内ごとに1個とすること。
- 女性用便所は20人以上ごとに1個とすること。
- 便池は、汚物が土中に侵入しない構造とすること。
- 手洗い設備は、流出する清浄な水を十分に供給すること。
第18条
- 洗面設備を設けること
- 被服汚染の作業は更衣室を設けること
- 被服湿潤の作業は乾燥設備を設けること。
休養
第19条
休憩の設備を設けるよう努めること
第20条
睡眠を与える必要のあるとき、睡眠又は仮眠の設備を設けること
第21条

50人以上又は女性30人以上で休養室又は休養所を男女別で設けること
第22条
持続的立業で座ることのできる機会があるときには、いすを備え付けること。
救急用具
第23条

負傷者の手当に必要な用具、材料を備えることが必要です。
救急用具の種類は次の通りです(安衛則634条と同じ)
- 包帯、ピンセット、消毒薬
- 高熱物を扱う場合は、やけど薬
- 重傷者を生ずるおそれのある場合は、止血帯、副木、担架など