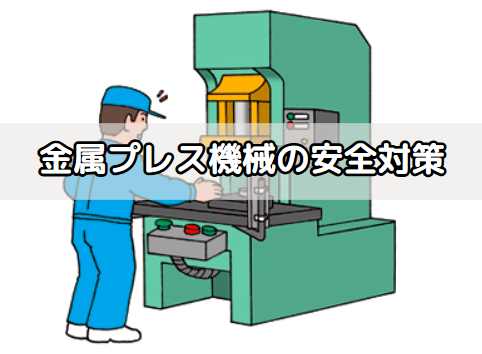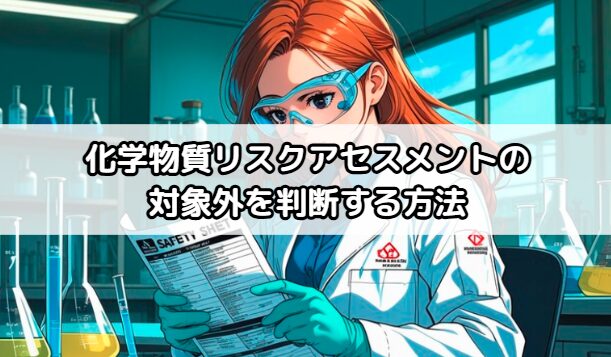「自分がどれだけ有害物質にさらされているか」を、あなたは正確に把握できていますか?
化学物質や粉じん、溶接ヒュームなど、目に見えないリスクが潜む作業現場において、従来の作業環境測定では把握しきれない“個人ごとのばく露リスク”が注目されています。
そこで今、厚生労働省も推進しているのが「個人暴露測定」です。2021年以降の制度改正と最新技術の進歩により、企業や現場での導入が加速中です。
この記事では、個人暴露測定の概要から導入手順、最新の法制度、補助金制度、そして見落とされがちな実務上のポイントまでを徹底解説します。
労働安全に携わるすべての方に向けた、実務に活かせる保存版ガイドです。
個人暴露測定とは何か
個人暴露測定(personal exposure monitoring)とは、ある個人が作業中にどの程度有害物質に曝露されたかを直接測定する手法です。従来の作業環境測定は作業場全体の空気環境を評価する方法でしたが、個人暴露測定は作業者ごとに異なるリスクを把握できる点が最大の特徴です。
2021年には、個人サンプラーによる測定(C測定およびD測定)が労働安全衛生法に基づく作業環境測定として正式に導入され、実施可能となりました。これにより、作業者の曝露状況をより精密に評価し、労働衛生対策に反映できるようになりました。

安全衛生法で定められている作業環境測定とは何が違うの??

作業環境測定も個人暴露測定も空気中の有害物濃度を測定する手法だよ。
作業環境測定は、測定対象場所のリスク低減対策を必要とする場所かどうかを評価する手法だよ。
一方で、個人暴露測定は、作業中に個人に測定器を装着して、個人が暴露する有害物の量を測定することで、健康リスクを評価する手法だよ。
なぜ今「個人暴露測定」が注目されるのか

以下のような社会的・技術的背景から、個人暴露測定は急速に注目を集めています。

ここ数年の化学物質の法律改正で化学物質のリスクアセスメントを導入する会社が増えてきているよ!
個人暴露測定により、実測値と管理目標値を比較して、健康リスクを評価する方法も立派なリスクアセスメントの手法だね!!
- 健康被害の未然防止
呼吸器疾患や発がん性など、微量でも長期に曝露することによるリスクが指摘されています。 - 制度の後押しと補助金
厚生労働省は2024年(令和6年度)より、「個人ばく露測定定着促進補助金」を創設し、企業や事業場が個人ばく露測定を導入する際の費用を支援しています。第1期は最大9千万円が配分され、全国労働衛生団体連合会が執行機関となっています。 - 技術革新
小型・軽量なウェアラブルデバイス、IoT機器、リアルタイム測定センサーの発達により、現場でのリアルなばく露データ取得が可能になりました。
測定対象となる主な有害因子
個人暴露測定の対象となる主な物質・因子は以下の通りです:
| 分類 | 測定対象物質 | 備考 |
|---|---|---|
| 化学物質 | 有機溶剤(トルエン、キシレン)、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド等 | 揮発性が高く吸入リスク大 |
| 粉じん | シリカ、アスベスト、溶接ヒューム | 肺線維症・発がん性が問題に |
| 金属類 | 鉛、クロム、ニッケル、カドミウム | 慢性中毒や神経系への影響 |
| 放射線 | X線、γ線、ラドン等 | 医療・原発・災害現場で使用 |
| 大気汚染物質 | PM2.5、NO2、オゾンなど | 屋外作業・都市部での影響 |
| 温熱環境 | WBGT(暑熱指数)、湿度 | 熱中症予防に有効 |
測定プロセスと標準手順(厚労省ガイドライン準拠)

個人暴露測定を使用したリスクアセスメントのガイドラインでは、測定は以下の流れで実施されます
- 事前調査:化学物質リスト、作業内容の確認
- SEG(同等ばく露群)の設定:同条件で作業するグループを設定
- 測定計画の作成:代表者5名以上、8時間測定が推奨
- 測定実施:サンプラー装着、業務中の全時間記録
- 評価:測定値と対象成分の管理目標値(許容濃度など)を比較し、評価する。
- 改善対策の検討:必要に応じ換気・作業変更
- 記録と報告:測定結果を3年間保存し、労働者に共有
実際の活用事例

● 製造・建設現場
粉じん・溶接ヒューム対策として、作業員に個人測定バッジを配布し、曝露実態の可視化とリスク管理に活用。補助金により装置購入・測定費用の負担軽減が可能。
● 医療機関(放射線技師)
放射線個人バッジによる累積被曝の管理。一定値を超えた場合は配置転換や休業措置がとられる。
● 福島第一原発事故の対応
避難住民や復旧作業員に対する放射線個人測定が行われ、被曝状況を証明する記録としても利用されました。
おすすめの個人暴露測定器
個人暴露測定器にも様々ありますが、使いやすさや測定可能物質の多さなどから、以下をおススメします。
【主な特徴】
・測定できる成分は約800程度
(有機物で蒸気やガスであれば、基本的に測定できます。)
(例)トルエン、アセトン、IPA、エタノールなど測定できます。
・測定値はppm表記
・防爆仕様(海外の検定を取得)
今後の展望:AI×個人ばく露測定
- リアルタイムリスク通知:スマホ連携で即時アラート
- AIによる健康予測:ばく露履歴+健康診断データから予測モデルを構築
- IoT連携による業務全体最適化:測定データに応じた作業シフトの自動調整
これにより、「測る」から「守る」時代へと進化しています。
まとめ
個人暴露測定は、単なる数値データの取得にとどまらず、労働者の健康、企業の安全管理、ひいては社会全体のリスク低減に直結する仕組みです。補助金制度や制度整備の流れを活用しながら、今後ますます活用が広がるでしょう。
企業の安全担当者や研究者のみならず、すべての働く人が「自分のばく露量を知る」ことが、自らを守る第一歩となるのです。築くための第一歩となるのです。